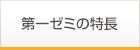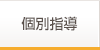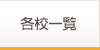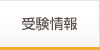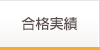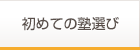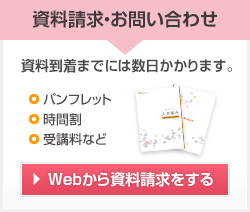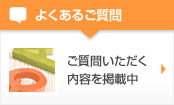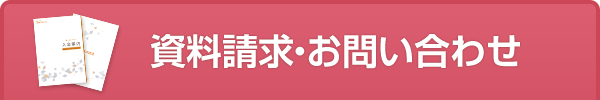- 現在位置
ホーム > 第一ゼミナールのさまざまな取り組み > 識字教育に取り組むボランティア活動「ユネスコ・世界寺小屋運動」
識字教育に取り組むボランティア活動「ユネスコ・世界寺小屋運動」
ボランティア活動「世界寺小屋運動」とは?
-
今、世界で約10億人の大人、その中でも女性は3人に1人が読み書きができません。
そのほかに学校に行けない子供たちが1億人以上います。
読み書きや計算ができることは今の世界で生きていくための基本的な条件なのです。 「ユネスコ・世界寺小屋運動」は1人でも多くの人々が学ぶ機会を得られるよう、日本に住む人々が自分たちにできることを考え、海外の人々のために協力していく運動です。 世界の大人の5人に1人が文字が読めません、彼らの暮らしについて考えてみましょう
-
具体的には、以下のような活動に賛同し、積極的に取り組んでいます。
 第一ゼミナールグループは、日本ユネスコ協会連盟の維持会員、エリーニ・ユネスコ協会の特別会員であり、ユネスコ協会で取り組んでいる種々の活動を14年にわたって支援しています。 ユネスコ協会では「世界寺子屋運動(教育を受けられなかった成人や学校に行けない子どもたちに教育の機会を提供する)」を積極的に推進しており、教育事業に関わる民間教育機関として、この活動を支援しています。
第一ゼミナールグループは、日本ユネスコ協会連盟の維持会員、エリーニ・ユネスコ協会の特別会員であり、ユネスコ協会で取り組んでいる種々の活動を14年にわたって支援しています。 ユネスコ協会では「世界寺子屋運動(教育を受けられなかった成人や学校に行けない子どもたちに教育の機会を提供する)」を積極的に推進しており、教育事業に関わる民間教育機関として、この活動を支援しています。
現在、アジア・アフリカなどの発展途上国では、文字の読み書きが不自由な人や学ぶ権利を奪われている人がたくさんいるという事実は皆さんもご承知のことと思います。 第一ゼミナールグループでは、民間教育機関としてそのような人々への勉強ができるきっかけ作りの手助けになればという想いで、「ユネスコ世界寺子屋運動」に賛同し、その運動の一つ、「書きそんじハガキ」の回収に毎年協力しています。
これは、生徒一人々々への気づきの教育の一環として、世界には勉強したくてもできない子どもが、たくさんいることを認識していただき、今の自分たちにもできることがあることに自ら気づいていくことにより、自分の恵まれた環境に感謝の気持ちを持てるようにすることに大きな意義があると実感しております。 そして、このような取り組みを通じて、“社会で活躍できる人づくり”につなげていきたいと思っております。
小・中・高校生の皆さん、皆さんの各ご家庭にある、たった1枚の「書きそんじハガキ」でも、以下のように世界中でこれだけ役に立ちます。 「書きそんじハガキ」を持っている人は、ぜひ、最寄りの第一ゼミナール・ファロスの各校まで持ってきていただければ幸いです。
- ※現在、この取り組みは終了しております。
-
- 世界の非識字者数(15歳以上の成人)約7億7400万人
- 正規の学校に通えない児童数(6歳から11歳の子供)約7200万人
- 非識字人口の大陸別割合ヨーロッパ0.8% アフリカ25% アジア69%オセアニア0.2% アメリカ5%
- 非識字人口の男女比男性36:女性64
- ※非識字者…文字が読めない、文字が書けない人々(教育を受けられなかった人々)
- どうして文字が読めないのだろう、学校へ行けないのだろう
-
9歳/男性/バングラディッシュ「ぼくの家はお金がなかったし、お父さんもお母さんも字が読めません。学校へ行きなさいとも言われませんでした。ぼくはそれが普通なのだと思っていました」12歳/女性/インド「女の子には勉強は必要ないという両親の方針で私は学校に行けませんでした。私は昼間くずひろいの仕事をして働いています」
上記は、ほんの一例です。
皆さんもテレビや新聞などを通じて、さまざまな国々の現状を見たことがあると思います。 他にも、学校へ行けない理由、文字が読めない理由にどんなことがあるか、自分なりに考えてみましょう。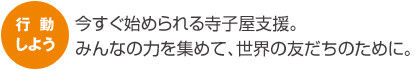
書きそんじハガキを集めよう
- 住所を書きまちがえたり、古くなって使えなくなったりした未使用の官製(年賀)ハガキを、集めてください。 50円の書きそんじハガキは、1枚45円の募金になります。
- 書きそんじハガキ1枚分(45円)で買えるもの
-
例えば、ネパールでは1ヶ月の生活費(家族6人)は、3,000円程度です。

- インドではノート1冊・鉛筆3本・消しゴム1個
- カンボジアではノート1冊・鉛筆4本
- アフガニスタンでは鉛筆6本
ユネスコ協会より感謝状が届きました
-
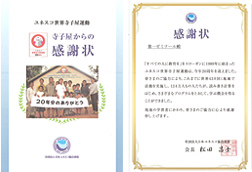
感謝状小・中・高校生、および保護者の皆さま、この度は日本ユネスコ協会連盟の「世界寺子屋運動」の一環として行いました「書きそんじハガキの回収」にご協力いただき、誠にありがとうございました。 日本ユネスコ協会連盟から別紙のような感謝状が届きましたので、ここにご報告させていただきます。
今回の活動において、第一ゼミ関連グループ合計で「3,790枚」の書きそんじハガキが集まり、世界各地でたくさんの子どもたちが勉強している「寺子屋」への大きな支援ができたと思います。 今後も第一ゼミグループは、アジアの子どもたちを中心に識字教育に取り組むユネスコの活動を、ユネスコ協会会員として支援していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

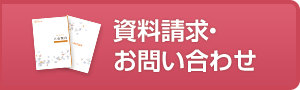




![お問い合わせ[受付時間 10:00〜19:00]0120-4119-01](/shared/images/str-header/freedial.jpg)