学校の授業以外の場所で、自ら内容を考えて取り組む自主学習。
小学生のお子さんの宿題として出されることも多いのではないでしょうか。自主学習は、小学生のうちにやり方を身に付け、習慣化することが大切だと言われています。
しかし、子供を自主的に勉強するように導くことは、なかなか難しいですよね。
この記事では、そんな小学生の自主勉強のやり方について詳しく解説します。
これを読めば、小学生のお子さんでも、楽しみながら自主学習に取り組み、ぐんぐん力を伸ばすことができます。ぜひ最後までお読みください。
いまの学力がわかる!伸びしろも見える!
【小・中学生 全学年無料】第一ゼミ公開テスト!

第一ゼミナールなら“はじめての塾”でも安心!
2週間無料体験実施中

小学生の自主学習のやり方で大切な2つのポイント

小学校で習う内容は、すべての学習の基盤になります。
また、小学生という発達段階は、身近な事象から多感に学びを得る時期です。この時期に自主勉強のやり方を身に付けておくと、その先の学習にも自発的に取り組むことができるようになります。
小学生の自主学習のやり方で大切なポイントは、以下の2つです。
- 意欲を引き出して前向きな気持ちで勉強する
- 積み重ねて習慣化する
なぜこの2つが大切なのかを解説します。
ポイント1. 意欲を引き出して前向きに勉強する
小学生の自主学習では、「学ぶ=楽しい」という概念を植え付け、子どもの意欲を引き出して前向きな気持ちで勉強することが大切です。
なぜなら、意欲こそが自主学習に取り組む動機となるからです。
例えば、勉強することによって得られる未来を想像させたり、子供の努力や成長を認めるなど、前向きになる言動で励ましてみましょう。子供は勉強に対してプラス思考になることができるはずです。
小学生の自主学習において、大人が上手に種をまき、意欲を引き出してあげることがとても大切なのです。
ポイント2. 積み重ねて習慣化する
小学生の自主学習のやり方として、もう一つ大切なことは、積み重ねるということです。
自主学習の積み重ねは、学習習慣の確立に繋がります。学習習慣がつくと、中学校から始まるテスト勉強や受験勉強にもスムーズに取りかかることができ、将来の自己実現が目指しやすくなります。
また、学校で習う学習のカリキュラムは、一つひとつの学習の積み重ねで組まれています。一つ取りこぼしてしまうと、その先の授業にどんどんついていけなくなってしまうことが多いのは、このためです。
学校で習ったことを自主学習で着実に身に付けていくことで、学習のつまずきをなくしていくことができます。
自主学習は勉強の習慣化に繋がる大事なステップと言えるでしょう。
小学生の自主学習における2つのポイントについて解説しました。それでは、この2つのポイントをおさえた自主学習とは、どのようなものなのでしょうか。
実際のやり方を、ポイントごとに分けてご紹介します。
小学生の意欲を引き出してプラス思考になる自主学習のやり方
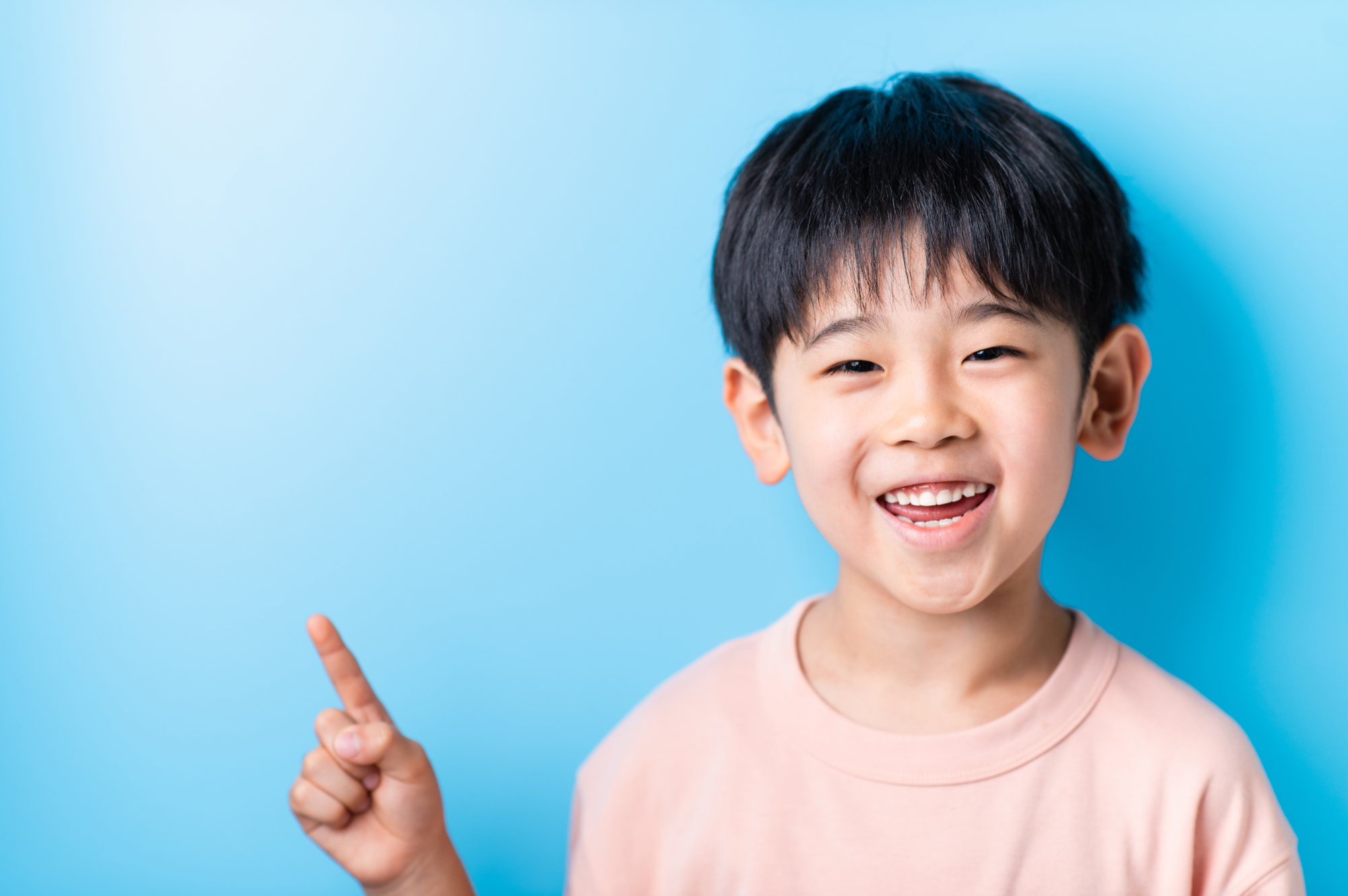
まずは、ポイントの一つ目「意欲を引き出してプラス思考になる」ための、自主学習のやり方です。
自主学習は、宿題のように「やらなければならないもの」と違い、意欲を引き出すことが難しいですよね。
小学生がプラス思考で取り組むための自主学習のやり方は、以下の通りです。
がんばりを「見える化」する
自主学習は、取り組むこと自体が素晴らしいことです。
内容や出来栄えよりも、まずは「がんばった」という事実を認めてあげることで、さらなる意欲を引き出すことができます。
そこでおすすめなのが、がんばりを「見える化」するやり方です。がんばりを「見える化」するやり方には、以下のようなものが挙げられます。
- 自主学習用のノートをつくり、これまでのがんばりを振り返れるようにする
- 取り組んだ課題に丸や点数をつけて、がんばりを数で見られるようにする
- 取り組んだページに、シールやコメントなどご褒美となるものを残す
このように、子供自身が「がんばった」「できるようになった」という実感をもてるようにすること、そして、それを親に認めてもらえていると感じられるようにすることが、小学生の意欲を引き出すためには、とても大切です。
親子のふれあいの中で学ぶ
これは特に、低学年や中学年の小学生に有効なやり方です。
自主学習は、単に机に向かって勉強することだけを指すのではありません。むしろ、小さい子供は、身の回りのさまざまなことに興味や疑問を抱き、そこから多くのことを学んでいきます。
この子供の興味や疑問を「学ぶ意欲」に上手に繋げていくことこそが、大人の役目。そこで大切なのは、親子のふれあいの中で学ぶ機会をつくることです。
例えば、子供がお母さんに「あれはなに?」と聞いてきたら、「なんだろう?なんだと思う?」と聞き返し、子供に考えさせます。そして、わからない時は、「一緒に調べてみようか」と本や動画などで一緒に勉強します。
このほかにも、一緒に地図を見て都道府県の名前を当てっこしたり、学校のワークのような問題を子供が作って親に出題したりと、小学生の自主学習は、親子でふれあいながら取り組めることがたくさんあります。
やり方一つで自主学習は、子供にとって意欲の湧くものになるのです。親子で一緒になって楽しく学ぶことを大切にしましょう。
「Iメッセージ」で喜ぶ
子供の意欲を引き出して前向きな気持ちにさせる声掛けとして、「Iメッセージ」というものがあります。
「Iメッセージ」とは、『わたし』を主語にしたメッセージのことです。「お手伝いしてくれてありがとう。お母さん、助かったよ。」というように、「お母さん自身がどう感じたか」を子供に伝えるものです。
反対に、『あなた』を主語にしたメッセージのことを「YOUメッセージ」と言います。
「YOUメッセージ」では、「あなた、ゲームしてばかりじゃない。少しは勉強しなさい。」など、叱ったり命令したりする口調になりがちです。こうすると、子供は「またか」と感じ、聞く耳をもたなくなる傾向があります。
子供の自主勉強に対する意欲を引き出すためには、この「Iメッセージ」を活用するやり方がとても効果的です。「自主勉強やったのね。お母さんもうれしいよ。」「こんなことができるようになったのね。うれしいな。」など、「うれしい」というメッセージを子供にたくさん伝えてあげましょう。
こうすることにより、子供は「喜んでもらえているから、もっとがんばりたい」と前向きな気持ちになり、やる気を出すことができます。
「Iメッセージ」でたくさん喜びを伝えて、子供の意欲を引き出していきましょう。
いまの学力がわかる!伸びしろも見える!
【小・中学生 全学年無料】第一ゼミ公開テスト!

第一ゼミナールなら“はじめての塾”でも安心!
2週間無料体験実施中

小学生が習慣化できる自主学習のやり方
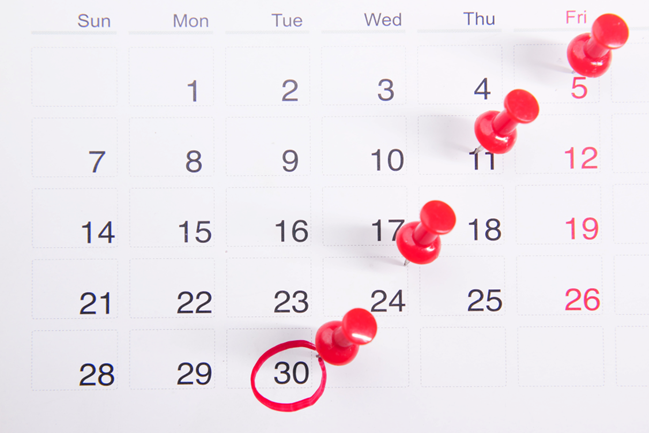
続いて、ポイントの二つ目「積み重ねて習慣化する」ための、自主学習のやり方です。
子供は、ゲームや遊びに夢中だったり、習い事が忙しかったりと、宿題以外の自主学習を習慣にすることは、なかなか難しいですよね。
では、小学生でも習慣化できる、自主学習のやり方とは、どのようなものなのでしょうか。
カレンダーに記録する
カレンダーに記録していくやり方は、とても有効的です。
ここで大切なのは、学年の発達段階に応じて、記録の残し方を変えること。
例えば、低学年のうちは、自主学習に取り組むということだけで、学習習慣を確立する大きな一歩になります。したがって、カレンダーへの記録も、「宿題以外の勉強をした日のところにシールを貼る」といった、ご褒美的な要素として行い、習慣化に繋げると良いでしょう。
一方、高学年になると、自分の得意・不得意を把握し、それらを踏まえて自主学習できるようになることが望ましいです。そのため、カレンダーに記録する際は、目標や学習予定、学習した内容などを具体的に記録していくことをおすすめします。
このようにして、発達段階を考慮しながらカレンダーに学習記録を残し、小学生のうちから自主学習への意識付けを行っていくと、自然と学習習慣を確立することができます。
課題のレベルを少しずつ上げる
小学生は、「わからない」「できない」と感じてしまうと、勉強を嫌いになってしまうことがあります。
一度勉強に拒絶感を覚えてしまうと、自主学習を習慣化することは難しくなるため、できる限りつまずきを感じさせないようにすることが鍵となります。
自主学習で子どもに問題を出す際は、その子のレベルより少し易しい課題から、徐々に難易度を上げていくようにしましょう。ワークなどに取り組む際も同様で、今日はこの単元、明日は次の単元というように、日に日にレベルアップさせていきます。
このように、一度に詰め込んで学ぶのではなく、ステップバイステップで課題に取り組ませることで、「できた」という達成感を味わわせることができるのです。
これは学校の授業でもよく使われる方法で、学力を定着させたり、学習習慣を確立させたりする効果があります。
小学生の自主学習におすすめの内容とやり方

「自主学習って何をやったらいいの…?」と困っている方も多いのではないでしょうか。
ここからは、小学生の自主学習の内容とそのやり方を科目別でご紹介していきます。
1. 国語
国語は、すべての学習の基本となります。
「読む」「聞く」「書く」「話す」の4つの力を、自主学習でバランスよく伸ばしていきましょう。
苦手な漢字の練習
テストで間違えた漢字を、大きく丁寧に書き直します。
ただ形を覚えるだけでなく、書き順や送り仮名もセットで覚えるようにしましょう。地道な自主学習ですが、積み重ねると大きな力になります。
教科書の視写
教科書の物語や説明文を、そのままノートに書き写します。
視写は、文章表現の技法を覚えたり、文章表記のルールを覚えたりするのに有効的です。段落や句読点など細部までよく見て、正しく写すようにしましょう。
ことわざや四字熟語、漢字の成り立ち調べ
言葉への興味は、国語力を伸ばす大きな要素になります。
小学生向けの辞典などで、ことわざや四字熟語、漢字の成り立ちなどを調べて、ノートにまとめましょう。このやり方は、楽しく言葉に触れ合うことができるため、おすすめです。
2. 算数
算数は、一つのつまずきから、その先の学習にどんどんついていけなくなってしまう子供が多い科目です。
自主学習で学習をひとつずつしっかりと身に付け、苦手をつくらないようにしましょう。
ワークやプリントの解き直し
ワークやプリントの間違えた問題は、そのまま放置せず、解き直すことが大切です。
どこでつまずいたかを分析し、同じ間違えをしなくなるまで、何度も解くようにしましょう。特に、分数・小数・割合などは、小学生がつまずきやすい単元なので注意が必要です。
文章問題作り
「文章問題が苦手」という小学生におすすめの自主学習は、自分で算数の文章問題を作ることです。
低学年であれば、大人が文章を作り、子供が数字を考えるなど、工夫して易しいやり方にします。子供が作った問題を家族で解き合うと、より楽しく文章問題を解く力を伸ばすことができます。
3. 理科
理科は、小学校3年生から始まる科目です。
低学年のうちは、「生活」という教科の中で、身近な植物や生き物との触れ合いを中心に学習します。理科の自主学習では、単なる暗記ではなく、実生活と結びつけながら楽しく学んでいくことが大切です。
まとめノート作り
授業で習ったことを、もう一度ノートにまとめると、学習内容をアウトプットすることができます。
授業のノートをそのまま写すやり方も良いですが、教科書や図鑑に載っているイラストを盛り込んで自分のまとめノートを作ると、より楽しく、より学びが深まります。
天気や月などの観察
授業の内容以外に、理科の自主学習としておすすめなのは、天気や月などの観察です。
身近な事象に興味や好奇心をもつことは、小学生の理科の学習においてとても大切なことです。観察したら、結果をノートに記録し、自分なりの考察や感想を書くようにしましょう。
4. 社会

社会も理科と同様、小学校3年生から始まる科目で、低学年のうちは「生活」として学習します。
自主勉強についても、やはり理科と同様、実生活との関連性をもたせ、興味を引き出すように工夫することが大切です。
まとめノート作り
暗記事項が多い社会の学習に効果的な自主学習は、授業で習ったことをノートにまとめ直すやり方です。
このやり方で勉強すると、学習内容を深く落とし込むことができます。また、関連のあることを自分で調べてまとめるなど、さらに質の高い自主学習へとステップアップできます。
都道府県調べ
社会は、実生活との結びつきが強い科目のため、自主学習としてできることはたくさんあります。
中でも、小学生に特におすすめなのは、日本の都道府県についての学習です。都道府県の場所や県庁所在地、各都道府県の特産品などを調べてまとめたり、親子でクイズを出し合ったりすると、楽しく学ぶことができるでしょう。
5. 外国語
外国語は現在、小学校でも必修科目となっています。
子供にとって「わからないもの」を学ぶことは、ハードルが高いものです。自主学習では、「正しく」よりも「楽しく」英語に親しむやり方をしていきましょう。
アルファベットの書き方練習
アルファベットを覚えることは、英語の「書く」学習の基本です。
最初はなぞって書き方を覚え、徐々にお手本をなくしていきましょう。多少不格好でも、がんばりを褒めてあげてハナマルをつけてあげることが大切です。
英語で自己紹介
「話す」ことへの抵抗感をなくすのに、英語での自己紹介をすることはとても有効的です。
子どもの学年に応じて、全体の長さや難易度を変えましょう。自己紹介を覚えたら、家族でたくさんコミュニケーションをとってみてください。あっという間に英語に親しむようになりますよ。
いまの学力がわかる!伸びしろも見える!
【小・中学生 全学年無料】第一ゼミ公開テスト!

第一ゼミナールなら“はじめての塾”でも安心!
2週間無料体験実施中

まとめ
本記事では小学生が楽しく学べる自主学習のやり方についてまとめました。
自主学習は、ついつい無理強いしてしまいがちですが、大人の導き方次第でいくらでも楽しくなります。
そして、そのやり方も無限にあります。お子さんの好きな分野や、お子さんが興味を示すやり方を見つけて、親子で楽しく自主学習に取り組みましょう。
この記事を参考に、お子さんの学ぶ意欲を引き出し、楽しくプラス思考で自主学習を習慣化させてください。