中学受験はお子さまにとっても、保護者の方にとっても大きな挑戦です。
しかし、誰もが中学受験で成功して、第一志望に合格できるわけではありません。思うような結果が得られないケースも少なくないでしょう。
本命校合格という狭き門を通過するには、保護者の方のサポートが欠かせません。
本記事では、中学受験に失敗する主な原因と対策、失敗した場合の対処法について解説します。お子さまが持つ可能性を最大限に引き出すために、適切な準備とサポートを整えて合格までの道のりをサポートしましょう。
※本記事での中学受験の失敗の定義は「入試に合格できない」こととします。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

小学生・自立学習コース4,620円~
2週間無料体験実施中
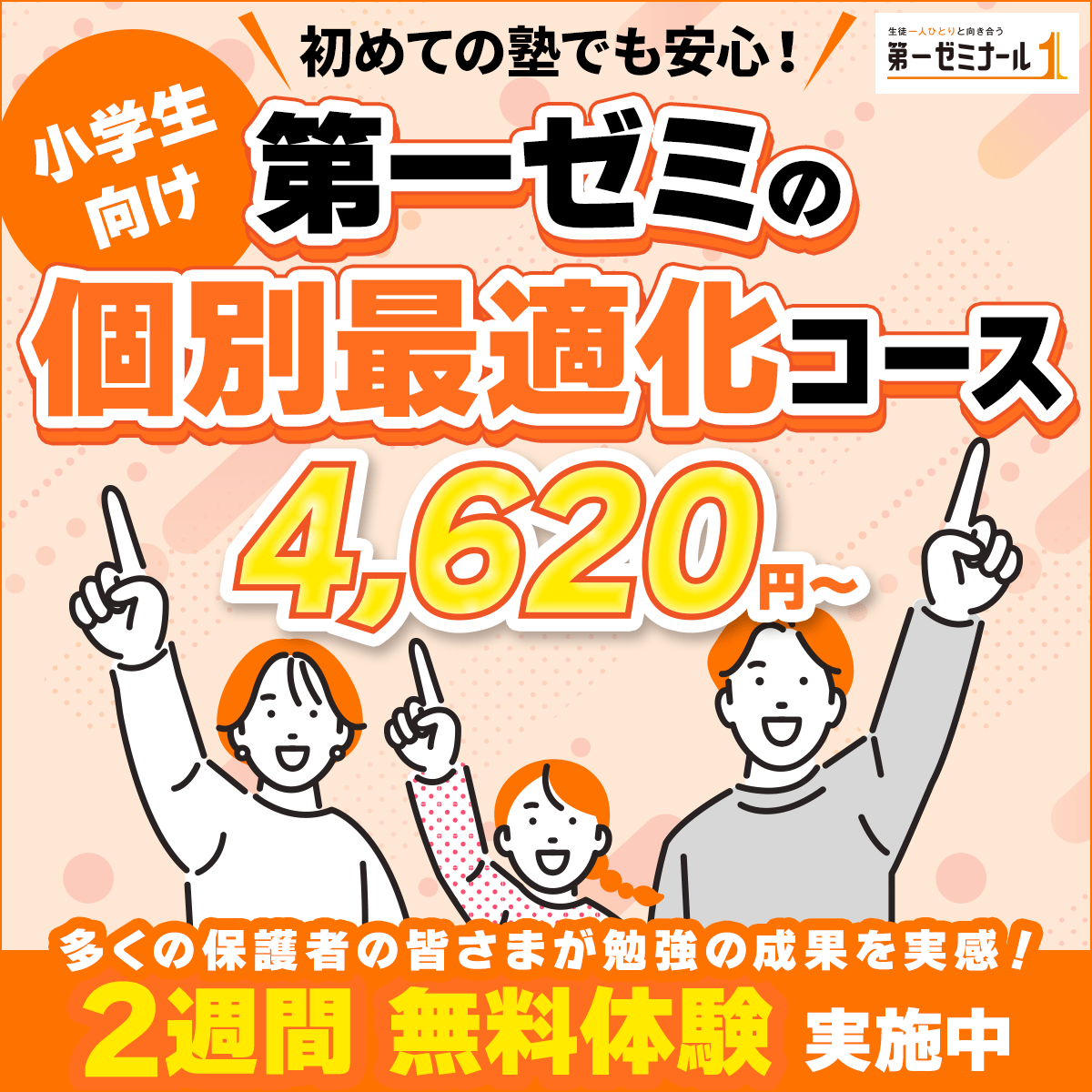
中学受験に失敗する原因

中学受験に失敗する主な原因は「準備不足」です。
ただし準備不足といっても、学力の不一致や出題傾向の分析不足といったさまざまなケースがあり、一概にはいえません。
まず最初に、中学受験失敗につながる具体的な例をあげて解説します。次のようなケースに当てはまらないかチェックしてみましょう。
志望校と学力の不一致
志望校がお子さまの学力に対して明らかに高すぎる場合、合格は難しくなります。中学受験では複数校の併願が一般的ですが、難関校ばかりを選びすぎると、すべて不合格になることがあります。
また、中学受験では保護者の方が志望校を決めることも多く見受けられます。まずはお子さまの現在の学力をしっかり把握し、適切な学校を選ぶことが重要です。
出題傾向の分析不足
偏差値だけで学校を選ぶと、入試問題がお子さまに合わず、不合格になることがあります。
同じような偏差値の学校でも、論理的思考力を問う問題が多い学校や、解答スピードを重視する学校など、出題傾向はさまざまです。
特に、中学受験では学校ごとの傾向が顕著なため、過去問を繰り返し解き、問題の傾向を把握することが大切です。塾の指導や問題集を活用しながら、志望校に合わせた効率的な学習を進めましょう。
勉強方法がお子さまにあっていない
勉強時間を確保していても、成果につながらない「やった気になっている」状態では、実力はなかなか伸びません。
特に注意が必要なのは、「勉強時間=学習成果」と考えてしまうことです。どれだけ長時間勉強しても、内容をしっかり理解していなければ意味がありません。
また、世間一般で「効果的」とされる学習理論や学習法でも、お子さまに合っていなければ十分な効果は得られません。たとえば、集中力や思考力が高まる時間帯として早朝が推奨されることが多いですが、朝が苦手なお子さまの場合、夜のほうが学習効率が上がることもあります。
さらに、適度な緊張感があったほうが勉強がはかどるお子さまは、個室よりも親の目が届くリビングでの学習が向いている場合もあります。このように、お子さまに合った学習環境や方法を見つけて勉強の質を高めることが、真の学力を身につけるために必要不可欠です。
すべり止め校を受験していない
第一志望校に固執しすぎて、すべり止め校を受験しないケースも失敗につながります。
1校も合格できずに受験を終えると、子供に大きなショックを与える可能性があります。すべり止め校の受験は、選択肢を増やすだけでなく、本番前の練習としても有効です。幅広い視点で受験校を検討することが大切です。
「絶対受かるから大丈夫」や「逃げ道をなくして本気にさせる」などの理由から、すべり止めを受験しないご家庭もあります。
しかし、たとえ学力的には十分でも、不合格になる可能性はゼロではありません。すべり止めがないことで必要以上に緊張して、お子さまが本番で実力を発揮できないケースもあるでしょう。
すべり止め校の受験は、選択肢を増やすだけでなく、本番前の練習としても有効ですので、最低でも1つはすべり止めを受けることをおすすめします。すべり止めは、合格の難易度がやや高い「チャレンジ校」、学力と同程度の「適正校」、合格見込みの高い「安全校」と、3種類を受験するのが理想的です。
本番で実力を発揮できない
いくら実力があっても、試験本番でパフォーマンスを発揮できなければ意味がありません。
当日の急な体調不良や精神的なプレッシャーなど、さまざまな理由が考えられますが、本番で緊張しすぎて実力を発揮できないケースが多いでしょう。
模試やすべり止め校の受験を活用して、本番に近い環境での経験を積むことで克服できます。
たとえ志望校が安全圏だったとしても過信はせず、本番でお子さまが存分に力を出し切れるように、日頃から体調面と精神面のケアをしましょう。
お子さまのモチベーションが低い
中学受験を進める上で、お子さま本人のモチベーションが低いと、計画通りの勉強が進まないことがあります。
中学受験は保護者主導になりがちで、お子さまのモチベーションが追いつかないこともあります。お子さまが受験への意義を感じられず、やる気を失うこともあるでしょう。
お子さまの目標を明確にし、受験のメリットを具体的に伝えるなど、親子でじっくり話し合うことが大切です。また、努力を評価し、小さな成功体験を積ませることで意欲を引き出すことも、モチベーションを上げるのに効果的です。
保護者の方が中学受験失敗の原因になるケース
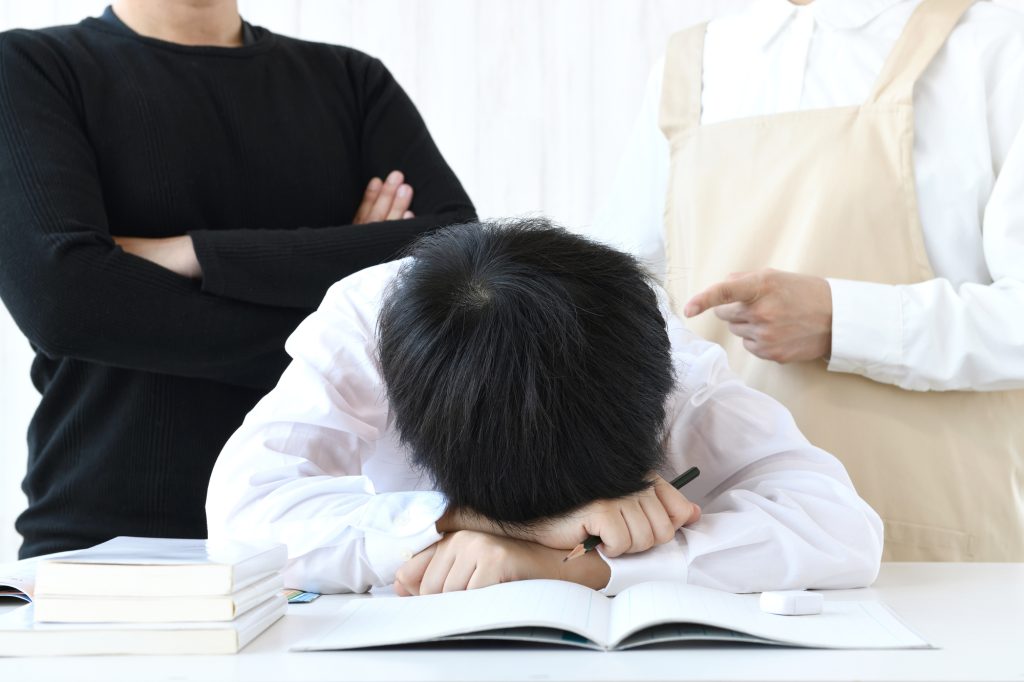
熱心になるあまり、保護者の方の行動が中学受験失敗の原因になる可能性もあります。
受験するのはあくまでお子さまであることを理解し、保護者として適切な距離を保ちましょう。ここでは、保護者の方が中学受験失敗の原因になるケースを解説します。
干渉しすぎる
保護者の方に過剰に干渉されると、受験勉強が「親にやらされているもの」となり、お子さまは受験勉強に嫌気が差してモチベーションが下がります。
代表的なのは、毎日の勉強時間の管理や勉強科目、勉強時間以外の過ごし方などについて、保護者の方が全て決めるケースです。
保護者の方がやるべき生活面や体調面は管理してあげて、その他は、一度思いきってお子さまに任せてみましょう。保護者の方は、適度な距離を保ちながら見守り、困ったときに手助けをするというスタンスを心がけることが大切です。
過度なプレッシャーを与える
保護者からの過度なプレッシャーは、受験勉強を頑張れなくなったり、試験当日に緊張して実力が出せなくなったりする原因の1つです。
「本当に勉強したの?」のような、お子さまの努力を否定するような言動や、「○○ちゃんなら絶対受かるよね!」という絶対的な期待をよせるのはやめましょう。お子さまが安心して受験に臨めるように、日頃から「失敗しても大丈夫」と思える環境づくりをしてあげてください。
もちろん、お子さまを注意すべき場面もあります。「出来ていない部分」や「その理由」をわかりやすく示してあげて、お子さまの気持ちに寄り添い、精神的なサポートを忘れないよう心がけましょう。
情報不足や誤った情報に頼る
中学受験は情報戦と言われるほど、正確でタイムリーな情報収集が合否を左右します。
保護者の方が受験に必要な情報を十分に集めていなかったり、インターネットや口コミなどの不確かな情報に頼ると、志望校選びや受験対策の方向性を誤ることがあるでしょう。
たとえば、志望校の出題傾向や求められる学力レベルを知らないまま勉強を進めると、的外れな学習になりかねません。また、塾の情報や模試の結果を適切に活用しないことで、受験計画が不十分になる場合もあります。
正しい情報を得るためには、学校説明会や塾のアドバイス、過去問の分析などを積極的に活用し、信頼できるデータに基づいて判断することが大切といえます。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

中学受験に失敗しないための対策法

中学受験に失敗しないためには、まずはお子さまの学力に合った志望校を選ぶ必要があります。その上で、お子さまが心のゆとりを持って本命校の受験に臨めるように、万全の準備をしましょう。
ここからは、中学受験に失敗しないための対策法を解説します。
志望校選びは家族全員で納得して決める
お子さまの意志を無視した志望校選びは、お子さまの受験へのモチベーションを低下させます。一方で、お子さまの意志を尊重しすぎると、憧れや理想だけで学校を決めてしまい、自分に合っていない学校を選ぶ恐れがあります。
偏差値だけにとらわれず、学校の教育方針や通学のしやすさ、校風がお子さまに合っているかを確認してください。親子で複数の志望校について入念にリサーチして、家族全員が納得できる決定をしましょう。
説明会や文化祭に参加して、実際の学校の雰囲気を知ることも選定に役立つのでおすすめです。
本命校の前に最低1つ合格を確保する
本命校受験の前に、1校でも合格していると、お子さまが自信を持って本番に臨めます。また、「ここに落ちても他がある」と思えることで、力みが抜け、試験で実力を発揮しやすいでしょう。
また、滑り止め校の受験を通じて、試験の流れや会場の雰囲気を体験できるため、本番の緊張感を軽減する効果もあります。
本命前に合格を確保するのが望ましいですが、本命校とすべり止め校の受験日が近すぎると、お子さまの負担になりかねません。中学受験は例年、秋頃に願書が出揃うため、受験日をチェックしてお子さまに負担のない日程で受験校を検討しましょう。
本試験に近い環境でプレッシャー慣れしておく
試験当日に、会場の独特な雰囲気に呑まれないよう、前もって入試に近い環境でお子さまをプレッシャーに慣れさせることが大切です。
試験を解く際の時間配分の練習や、試験会場特有のルールに慣れておくことで、当日の不安を軽減しやすくなります。塾や学校の模擬試験や受験予定の「プレテスト」を積極的に利用しましょう。
中学受験向けの模試は、3~4年生から受験を始めるのが一般的です。現在の学力を把握するためにも、継続して受験することをおすすめします。6年生になると、模試の受験頻度を増やすことが望ましく、前半(3~8月)は2~3回程度、後半(9月以降)は月1回のペースで受験するのが理想的でしょう。
志望校に足を運んでモチベーションを高める
実際に志望校に足を運んで、受験へのモチベーションを高めましょう。実際の雰囲気を知ると、お子さまが入学後の具体的なイメージを持てるため、受験勉強にも熱が入りやすくなります。
オープンキャンパスや説明会に参加し、通ってる学生や先生と話す機会があれば、不安の解消や目標意識の向上につながることもあります。
訪問が難しい場合は、学校紹介資料の活用がおすすめです。最近では、SNSなどで学校や部活動の様子を紹介している学校も多く、学校について知る機会が増えています。こうした情報を積極的に活用し、お子さまの「合格したい」という意欲を高めるきっかけにしましょう。
生活管理・体調管理を徹底する
お子さまの生活管理・体調管理は、保護者の方の最大の仕事とも言えます。
特に、お子さまは勉強のために食事や睡眠の時間を削りやすいため、疲れが溜まらないように、保護者がしっかりと監督しましょう。
栄養バランスの良い食事を心がけ、毎日同じ時間に起床・就寝させるのが理想的です。睡眠時間が短くなる場合は、身体を温めてベッドに入れるなど、睡眠の質を上げる工夫をしましょう。
あわせて、保護者の方の体調管理も重要です。保護者の方が体調を崩すとお子さまのお世話どころではありません。万全にサポートできるよう、ご自身の健康にも注意してください。
適度に息抜きできる環境を作る
お子さまのやる気や集中力を維持するには限界があります。たとえば、長時間勉強する場合には、40~50分ごとにリフレッシュしてあげましょう。
次のような息抜き法がおすすめです。
- 勉強場所を変える、外の空気を吸う
- ストレッチなど軽い運動を取り入れる
- 家族団らんで会話を楽しむ
- おやつなど好きなものを食べる
休憩時間を楽しむことで、次の学習に向けたエネルギーが生まれます。
一方で、あまりおすすめできない息抜き法は、ゲームや動画配信サイトの視聴です。これらは脳が興奮して疲れやすくなり、休憩の効果が出にくくなりますので注意してください。
中学受験に失敗したお子さまへのNGな接し方

中学受験は誰もが努力して挑むものですが、どれだけ頑張っても全員が合格できるわけではありません。
しかし、志望校に不合格だったとしても、中学受験に失敗したとは言い切れません。結果が出なくても、頑張って受験勉強したことは、お子さまや家族にとって大きな意味があります。
お子さまの心に大きな傷を残さないように、受験失敗後は適切かつ入念にケアしましょう。
保護者の方が落ち込みすぎない
中学受験の失敗に対して、保護者の方自身が過度に落ち込むと、その気持ちはお子さまにも伝わります。
お子さまに「親をガッカリさせた」という罪悪感を植え付けやすく、さらなるプレッシャーを抱えてしまうことがあります。お子さまの前では落ち込む姿を見せず、前向きな姿勢で接してあげてください。
保護者の方のショックを軽くするには、受験前から気持ちの整理をしておくのがポイントです。中学受験はあくまで通過点の1つに過ぎず、不合格だとしても「人生の失敗ではない」や「結果よりも努力したことに価値がある」と理解しておきましょう。
挑戦を否定しない・ネガティブなことを言わない
中学受験の失敗を受けた際、保護者の方が挑戦自体を否定したり、ネガティブな発言をすることは、お子さまの自己肯定感を大きく傷つける原因になります。
「あなたには無理だったね」や「あの学校を受験したのが間違いだった」といったお子さまの挑戦を否定するような言葉は、お子さまを傷つけてしまいます。
お子さまの良かったところ・悪かったところを客観的に評価してあげてください。「ここまで頑張ったことがすごいね」とポジティブな言葉をかけて、努力や挑戦の過程をしっかりと認めてあげましょう。
次の目標へ気持ちを切り替えさせる
お子さまが結果を引きずっている場合は、次の目標を設定して気持ちを切り替えさせましょう。いつまでも落ち込んでいては、他のこともうまくいかなくなるためです。
次の学校生活や目標に目を向けさせるように、中学で部活を頑張る、勉強で学年10位以内に入るなどの目標を一緒に設定してあげてください。また、「この学校ではこういうことが学べるよ」といった前向きな情報を共有することで、お子さまが次のステップに期待を持てるようになります。
不合格という結果にこだわりすぎず、お子さまの気持ちを切り替えて心の負担を軽くしてあげましょう。
中学受験では保護者の方は1番の理解者でいよう

中学受験では、保護者の方はお子さまの1番の理解者でいてあげてください。成績不振だとつい叱りたくなりますが、お子さまが決して怠けているわけではない場合、頭ごなしに叱るのは避けましょう。
成績不振の原因が単なる勉強不足ではなく、不安やプレッシャーからきている可能性もあります。お子さまの立場になって気持ちを想像して共感することで、心の支えになります。その上で冷静にアドバイスをすることで、お子さまは安心感を得て、受験に前向きに取り組むことができます。
とはいえ、大切なお子さまの中学受験となると、保護者の方自身も余裕を失うことがあるでしょう。
そんなときは、学習塾への入塾を検討するのも一つの方法です。
プロの指導に勉強面を任せることで、保護者は体調管理や生活サポートに専念でき、自身のストレスを軽減することもできます。また、実績のある塾で本格的な受験指導を受けられることは、お子さまにとっても大きなメリットとなるでしょう。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

まとめ
中学受験で失敗する原因の多くは「準備不足」です。実力に見合わない志望校選びや、問題傾向の分析不足、本番に慣れていないゆえのプレッシャーなど、合格を勝ち取るために必要な準備が不十分であるケースが多く見られます。
お子さまに合った志望校を選び、滑り止め校の受験を計画するとともに、当日の流れや注意点を事前にしっかり確認しておくことが大切です。本番でお子さまが最大限の実力を発揮できる環境を作りましょう。
保護者の方はお子さまが安心して試験に臨めるよう、1番の理解者として寄り添いながらも、適切な距離感を保ちつつサポートすることが求められます。
もし、サポートが難しい場合は、中学受験の実績が豊富な学習塾を利用することをおすすめします。学習塾を活用することで、保護者の負担やストレスを軽減しながら、お子さまが最適な環境で勉強に取り組むことができます。狭き門である中学受験を突破するために、お子さまに合った学習塾を慎重に選びましょう。