小学校における英語教育のあり方が、近年変わりつつあります。
すでにご存知の保護者の方も多いと思いますが、これまで中学校から行われていた英語教育が、2018年より小学5年生から必修科目として導入されました。この目的は、将来的に英語で討論や交渉などのコミュニケーションをとれるようになること。
今後ますますグローバル化が進む日本社会において、英語で対話をし、互いに協力しあって活動できるよう、英語技能の強化が目指されています。
この夏、合格への「ドア」を開けてみませんか?
第一ゼミナール 2025夏期講習会

小学生指導がパワーアップ!
最先端のAI&ICTの活用で最適な学習を提供

小学校における英語教育必修化への流れ
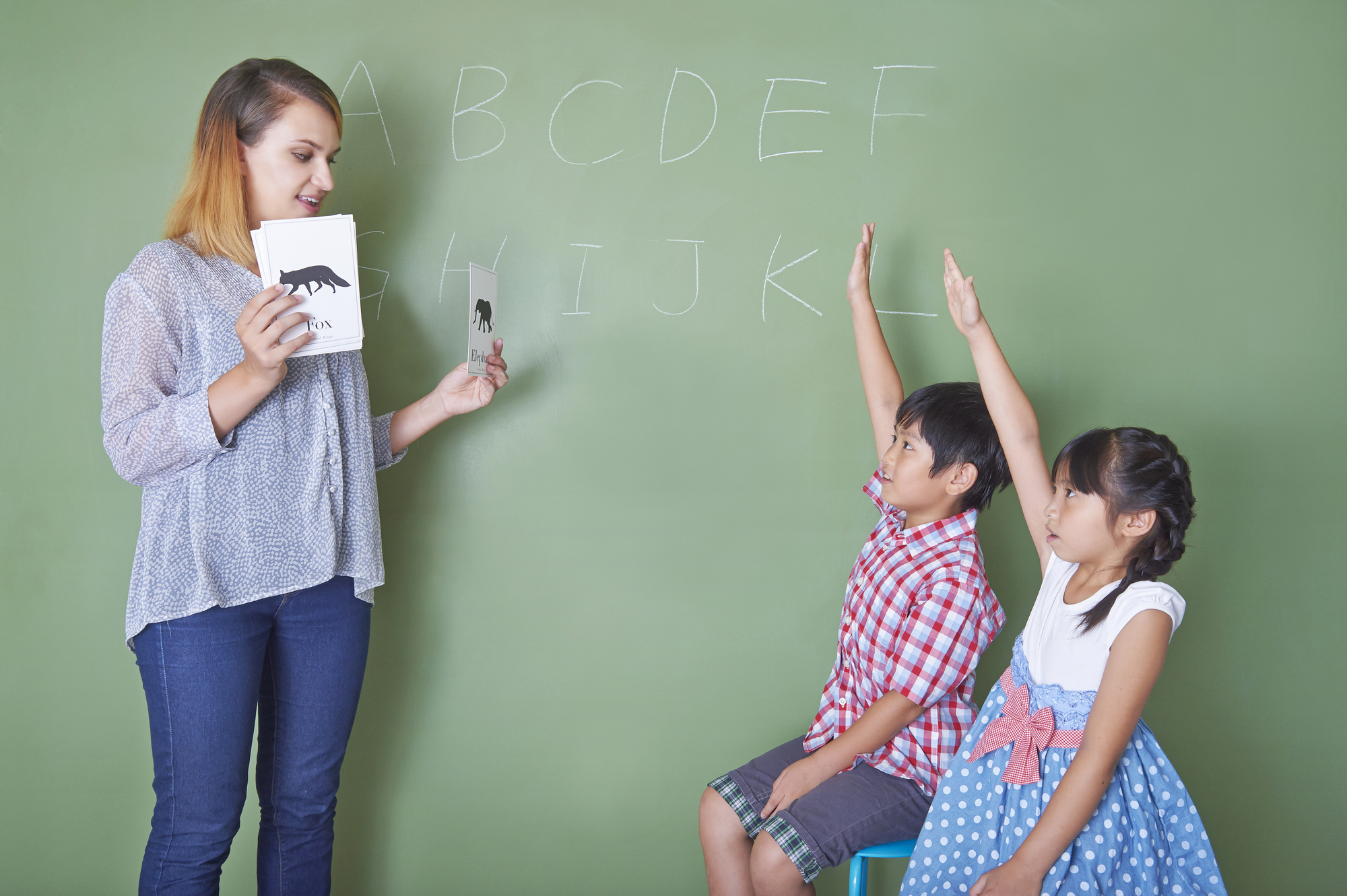
2008年度、小学5、6年生を対象に「外国語活動」始まる
小学校における英語教育は、2008年から取り入れられています。
ただし、2008年の時点では「教科」としてではなく、「外国語活動」と銘打った「英語に親しむためのアクティビティ」としての導入でした。
対象は5年生と6年生。
英語を使ったレクリエーションやゲーム、ネイティブスピーカーとの交流などといった活動を通し、中学校に入って本格的な英語教育を受ける前に「英語に慣れておこう」という目的で行われてきました。
2011年度、5、6年生を対象とした英語教育が必修化
小学校における英語教育は、2011年度には「外国語活動」として必修化され、現在では5年生・6年生で英語を習うということが定着化しています。
とはいえ、現在の英語教育の目的は、あくまでも「英語に親しむこと」や「海外の文化に興味関心を持つこと」、「英語を使うという姿勢を養うこと」に重きが置かれています。
そのための取り組みとして教育現場で行われているのは、歌やゲームを通じて英語を使ったり、ロールプレイングゲームを通じて挨拶や定型文を習ったりなどの活動です。子どもたちはレクリエーションの延長線上で楽しく英語を学んでおり、小学校の英語教育現場では和やかな空気で授業が展開されているようです。
一方、中学校での英語教育で行われている、英単語のスペルや文法、読み書きを覚えるという指導はほとんど行われていません。
つまり、現在の小学校における「外国語活動」としての英語教育では、英語を「勉強する」という段階には踏み込んでいないのです。
2018年より、3年生から英語教育が必修化、5・6年生では成績がつく教科に
そんな中、2013年末、文部科学省から小学校における英語教育の新たな方針が打ち出されました。
ここで定められているのは、東京五輪が開催される2020年を目指して小学校での英語教育をさらに拡充させていくという内容。
たとえば、これまで5年生から開始されていた外国語活動としての英語の授業を3年生からに前倒し、5年生以降は国語や算数と同様に成績がつく教科として導入されるようになります。つまり、5年生以降では、検定教科書を使った授業が行われ、定期テストが実施されることになるのです。
必然的に、これまでのように「英語に親しむ」だけでなく、実践的に英語を「使える」ように、単語のスペルや文法、読み書きを習得することが必要とされます。
また、これらの変更を受け、中学入試の受験科目に英語を加える動きが活発化しています。2016年には、首都圏の私立中学の63校が、なんらかの形で英語の試験を実施しました。
この夏、合格への「ドア」を開けてみませんか?
第一ゼミナール 2025夏期講習会

小学生指導がパワーアップ!
最先端のAI&ICTの活用で最適な学習を提供

英語教科の本格導入を前に家庭でしておきたいことは?

英語は、数学や理科、社会といった他の科目とは少し性質が違うものです。
なぜなら、英語は「言語」であるから。
わたしたちの多くは、母国語である日本語を身につける際に単語や文法から入ったわけではなく、成長過程において耳にする言葉、目にする文字を自然と習得してきています。単語や文法を論理的に理解するようになったのは、その後のこと。言語を習得する際には、このような順序が最も適切であり自然なのです。
ですから、英語を勉強する際にも、いきなり英単語や文法に入るより、まずは「自然と英語に触れる」という段階を踏むことが大事だといえます。
そのための取り組みとして小学校でも3年生から英語での初歩教育が取り入れられていますが、ご家庭でも並行して英語に触れる機会を設けるようにしましょう。
たとえば、英語の絵本を読んだり、英語の音楽を聴いたりDVDを観たりして、子どもの感性に訴えるような手法で英語を身近に感じさせましょう。