中学1年生にとって初めての中間テストは、今後の成績や高校受験に大きな影響を与えるため、非常に重要なテストです。
特に中学1年生の1学期中間テストは、基礎的な内容が中心で高得点を取りやすい特徴があります。しかし、闇雲に勉強しても良い結果にはつながりません。効率よく勉強し、高得点につなげるためには、ポイントを押さえた学習が必要です。
この記事では、新中学1年生が初めての中間テストで高得点を取るためのコツや、避けるべき勉強方法を詳しく解説します。
中1の初めての中間テストが大事といわれる理由
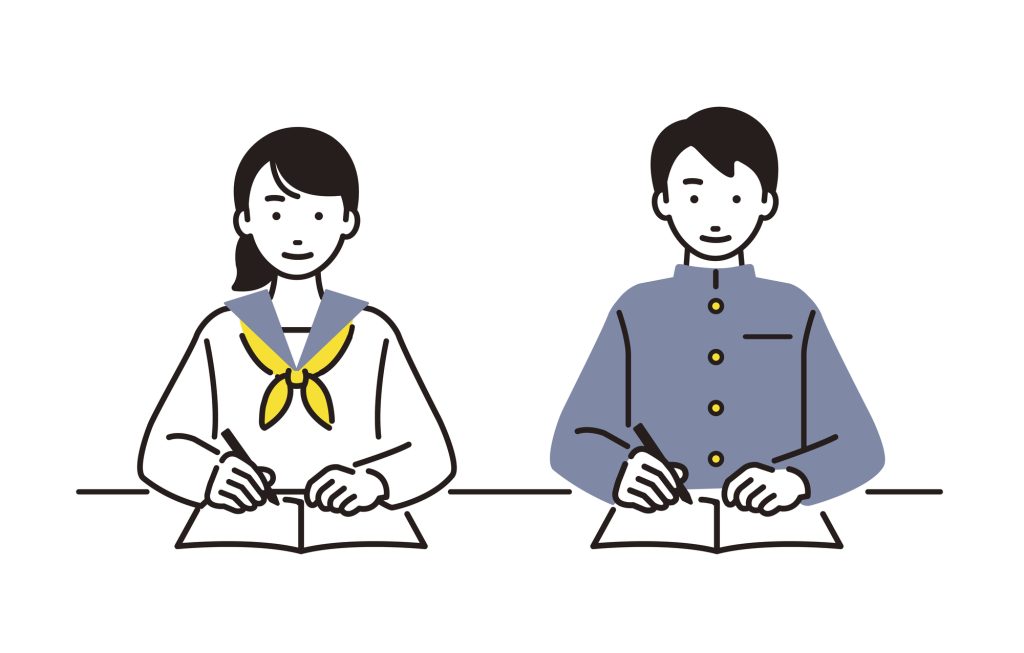
初めての中間テストは、これからの3年間の成績・内申点、そして高校受験にも大きく影響します。
特にこの初めてのテストで良い結果を出すことで、「自分にもできる!」と自信を持ち、今後の学習へのモチベーションを高めることができます。
また、中間テストの点数は成績に直結し、その後の通知表・内申点にも影響を与えます。もし、最初のテストでつまずき、その後も成績が上がらなければ、内申点が不足し志望校の受験が難しくなる場合もあります。
つまり、最初のテストで高得点を取ることが、高校受験の選択肢を広げるうえでも大切だといえるでしょう。
中1の初めての中間テストの特徴
1学期中間テストは、これ以降の定期テストに比べて範囲が狭く、基礎的な内容が中心です。そのため、計画的に勉強すれば誰でも高得点を取りやすいテストです。
勉強した分だけ結果が出しやすいテストでもありますので計画的に準備を進めていきましょう。
時期・科目・範囲
1学期の中間テストの時期・科目・範囲は次の通りです。
- 時期:5月中旬~下旬
- 科目:国語・数学・英語・理科・社会
- 範囲:小学校の復習、および中学入学後に学習した内容
中学校入学後は、ガイダンスや学校行事が多いため、授業の進み具合は比較的ゆっくりです。そのため、1学期中間テストは中学3年間の中でも特に範囲が狭く、事前に予測しやすいテストでもあります。
テスト範囲はゴールデンウィーク明けに発表されることが多いですが、ある程度は事前に把握できるため、早めに対策を始めるのがポイントです。特に、多くの新中1生がつまずきやすい数学や英語は、余裕を持って勉強を進めておくと良いでしょう。
小学校のテストとの違いは?
中学校の定期テストは、小学校のテストと比べていくつかの大きな違いがあります。中でも、最も大きな違いはテストの実施タイミングです。
- 中学校:テスト期間内に複数の教科を一度に実施
- 小学校:各単元ごとにテストを随時実施
小学校では、教科ごとにテストが行われていたため、直前の勉強でも対応できることが多かったかもしれません。しかし、中学校では一度に複数の教科のテストが実施されるため、効率的に学習し、計画的に準備する力が求められます。
初めての中間テストは範囲が比較的狭いとはいえ、小学校に比べると学習量は増えるため、効率的に進めることがカギです。
中1の初めての中間テストで高得点を取るコツ

中1の初めての中間テストで高得点を取るには、テスト4週間前を目安に計画的に勉強を始めることが大切です。
得意科目はできるだけ早めに仕上げ、苦手科目の克服に集中することがポイントです。
1. 勉強開始は3~4週間前
定期テストの勉強は、テストの2週間前に始めるのが一般的です。しかし、中1の1学期の中間テストに関しては、最低でも3週間前から取り組むのが理想です。
初めてのテスト勉強では、自分に合った勉強法や時間配分がまだ確立されていないため、スムーズに進まないことがあります。その結果、勉強時間が足りずに十分な対策ができないという事態にもなりかねません。
テスト範囲表が配られるのは、たいてい試験の1週間前です。そのため、「テスト範囲が分からないから勉強できない!」と思い込み、準備が遅れてしまうケースがよくあります。しかし、この思い込みは大きなワナです。
範囲が発表される前でも、定期テストには学校の授業で学習した内容が出題されます。特に、英語や数学のような積み重ねが重要な科目は、どこが出題されるか事前に予測しやすいため、早めに復習を始めることができます。
1学期中間テストは5月中旬以降に行われるため、4月中旬~下旬を目安に勉強を始めると安心です。テスト2週間前までは、ワークや配布プリントの解き直しを1日1時間ほど行い、基礎をしっかり固めておきましょう。
2. 日程と範囲を確認
テストの日程と範囲をしっかり把握し、優先的に取り組むべき内容を確認します。
どの教科が何日目の何時間目に行われるのかを把握し、ワークや配布プリントのどこから出題されるのかを確認することで、勉強の計画が立てやすくなります。
テスト前の授業で教師が「ここから出る」と口頭で伝えることもあります。こうした情報は出題される確率が非常に高いため、必ずメモを取り、重点的に復習して点数の取りこぼしを防ぎましょう。
3. 教科書・ワーク・配布プリントを中心に学習
中学校の定期テストでは、授業で使用した教科書・ワーク・小テストや配布プリントからの出題が中心になります。
ワークやプリントの問題がそのまま出題されることも多いため、解き直しを徹底して解法をしっかり身につけることが重要です。
効率的な学習サイクルは以下の通りです。
1 ワーク・プリント1周目:全ての問題を解き、現在の正答率を把握
2 解けなかった問題の復習:解答・教科書を確認し、ピンポイントで解き直す
3 ワーク・プリント2周目:1周目より正答率が上がっているかを確認
4 再び苦手問題を復習
5 ワーク・プリント3周目:完全に解ける状態を目指す
6 解けない問題がなくなるまで繰り返す
ピンポイントの解き直しと全体の解き直しを繰り返すことで、苦手な問題を減らし、得意な問題は確実に得点源にできます。
何度も解き直し、テストまでに解けない問題がない状態にするのが理想的です。
4. 暗記は2週間前から始める
暗記が必要な科目(理科・社会・英語)は、少なくとも2週間は確保するようにしましょう。
特に初めての中間テストは暗記問題が多いため、しっかり時間をかけて対策することが大切です。暗記時間が足りず、本番で覚えきれなかった内容が得点につながらないのは非常にもったいないことです。
効果的な暗記方法として以下の通りです。
- 書くだけでなく、声に出して覚える(視覚・聴覚の両方を活用)
- 朝や寝る前に復習する(記憶が定着しやすい時間帯)
- 何度も繰り返す(1回ではなく3回以上復習する)
英単語を覚える際には、発音とスペルをセットで覚えることも重要です。教科書やワークの文章を音読しながら暗記すると、より定着しやすくなるのでおすすめです。
5. 最後の1週間は苦手な科目・分野を重点的に
これまでの学習を計画通り進めていれば、テスト直前の1週間前には得意科目や暗記科目の基礎はほぼ仕上がっている状態になっているはずです。
この時期は、解ける問題を何度も繰り返すのではなく、苦手な問題を徹底的に克服することが重要です。
- 過去に間違えた問題を重点的に解き直す
- 苦手な分野をリストアップし、集中して復習する
- 時間を計って模擬テスト形式で解く
テスト前日には、翌日の教科の見直しに時間を使うようにしましょう。本番で焦らずに解けるよう、最後の仕上げを意識した勉強をすることが大切です。
避けるべき勉強方法

良かれと思って取り組んでいる勉強法が、実は効率を下げる原因になっていることがあります。時間をかけているのに成績が伸びないと感じている場合、勉強のやり方を見直すことが大切です。
ここでは、避けるべきテスト勉強方法を解説します。
1. 睡眠時間を削る
テスト前になると、夜遅くまで勉強することが良いと思いがちですが、実は逆効果な場合が多いです。寝不足は集中力や記憶力を低下させ、効率的に学習ができなくなります。
特に中学生は成長期であり、1日最低8時間の睡眠が推奨されています。たとえば、朝7時に起きる場合は夜11時には就寝するのが理想的です。十分な睡眠をとることで、学んだ内容がしっかり記憶に定着します。
2. ノートのまとめ直し・教科書のマーカーの引き直し
ノートをまとめ直したり、教科書にマーカーを引き直したりすることは、ノートをきれいにすることや、教科書を見やすくすることが目的になりがちで、内容そのものは頭に入っていないことが多いです。
大切なのは、勉強した「気分」になることではなく、確実に知識を身につけることです。ノート整理よりも、解けなかった問題を解き直し、理解を深めることに時間を使いましょう。
3. テスト直前に新しい問題集を買う
「もっといい問題集があるかも」と思い、テスト直前になって新しい問題集を買うのは避けましょう。
新しい教材を使うと、解き慣れない問題に時間を取られ、理解が浅くなってしまいます。買っただけで満足して、結局活用しきれないケースも出てくるでしょう。
定期テストは、授業で使った教科書・ワーク・プリントからの出題が中心です。まずはこれらを完璧にすることを優先しましょう。新しい問題集に手を出すのは、基本をしっかり固めた後にするべきです。
4. 長時間ダラダラと机に向かう
「机に向かった時間=学習成果」と思い込むのは間違いです。長時間勉強していても、集中できていなければ意味がありません。
効率よく勉強するためには、以下のポイントを意識しましょう。
- 短時間でも集中して取り組む
- 単元ごとに小テストを行い、自分の理解度を確認する
- 何を勉強するか明確にし、ダラダラと時間を使わない
また、1時間~1時間半ごとに10分程度の休憩を取ると、集中力が持続しやすくなります。「次の休憩まで頑張ろう」というメリハリが生まれ、勉強の効率が上がります。
机に向かっている時間ではなく、どれだけ集中して学習できたかが大切です。短時間でも密度の高い勉強を心がけましょう。
保護者の方がやるべきお子さまへのサポート

前述のように、初めての中間テストの結果は中学3年間の学習習慣や成績に大きな影響を与え、高校受験の内申点にも関わってきます。
だからこそ、「初めてのテストだから仕方ない」と妥協せず、お子さまが良い結果を残せるよう、保護者の方の適切なサポートで後押しをしましょう。
1. 干渉しすぎない
中学生になったら、自主的に勉強を進める力を育てることが大切です。
「勉強したの?」「勉強しなさい!」と頻繁に声をかけるのは、お子さまの学習意欲を削ぎ逆効果になりやすいため、必要最小限に留めましょう。
保護者の方がサポートすべきなのは、勉強スケジュールの立案と管理です。実現不可能な計画を立てていないか、予定通りに進行しているか確認しましょう。
お子さまの自主性を尊重しながら、適切なタイミングでフォローすることが長期的な学習習慣の定着につながります。
2. 勉強に集中できる環境を整える
お子さまが勉強に集中しやすい環境を整えることも、保護者の方の大切な役割です。
- 勉強が終わった後すぐに食事やお風呂に入れるよう生活リズムをサポート
- テレビの音量を下げるなど、静かな学習環境を整える
もし、お子さまが勉強に集中できない場合は、必要に応じてスマホを預かるといった厳しめのサポートも必要かもしれません。
また、お子さまの性格や生活パターンに合わせた工夫も重要です。リビングでの学習が向いている場合は適度に見守る、一人で集中するほうが得意なら勉強スペースを確保するなど、状況に応じたサポートを意識しましょう。
3. 体調面・精神面のケア
テスト勉強が続くと、疲れやストレスが溜まりやすくなるため、体調管理とメンタルケアも重要になります。
栄養バランスの良い食事や、十分な休息と睡眠を取れるようにサポートしてください。軽い運動やストレッチを取り入れてリフレッシュさせる方法もおすすめです。
また、初めての中間テストは、お子さまにとってプレッシャーを感じやすい場面でもあります。「大丈夫?」「何か困っていることはある?」と、不安な気持ちを聞いてあげたり、解決するための勉強法を一緒に考えしましょう。
保護者の方の適切なサポートによって、お子さまが万全の状態でテスト本番に臨めれば、高得点も期待できます。
中1の初めての中間テスト結果が悪かったときは?

初めての中間テストの結果が悪くても、落ち込みすぎる必要はありません。大切なのは、原因を振り返り、次の定期テストに活かすことです。
例えば、特定の科目や単元でつまずいた場合は、復習不足が原因かもしれません。ワークやプリントをしっかり解き直したか、分からない問題を放置せず先生に質問したかなど、勉強の進め方を見直しましょう。
保護者の方は、結果ではなく努力した過程を認めてあげて、前向きな声かけを意識しましょう。テスト結果を次のステップにつなげることで、次回のテストではより良い成果を目指せます。
まとめ
中1の初めての中間テストは、今後の成績や高校受験に大きな影響を与える大切なテストです。範囲が比較的狭く基礎的な内容が多く、高得点を取るチャンスでもあります。
計画的に勉強を進め、効率的な勉強方法を実践することで、良い結果につなげることができます。まずは試験3~4週間前から準備を始め、教科書・ワーク・プリントを中心に学習を進めましょう。苦手な科目や分野を中心に、授業で使った教材を何度も解き直し、解けない問題がない状態にするのが理想的です。
お子さまが全力で中間テストに臨めるよう、保護者の方は適切な距離感でサポートしましょう。もし初めてのテストで思うような結果が出なかった場合でも、落ち込む必要はありません。大切なのは原因を分析し、次回のテストに向けて改善策を立てることです。
今回紹介したポイントを参考に、初めての中間テストで高得点を目指しましょう。