夏休みの恒例イベント、「青少年読書感想文全国コンクール」の季節がやってきました。読書感想文を苦手と感じているお子さまも多く、毎年頭を悩ませている保護者の方も多いでしょう。
この記事では、読書感想文を書くための本の選び方から感想文の書き方、苦手と感じているお子さまに向けた書き方のコツをご紹介します。
お子さまが楽しく、保護者の方も無理なく取り組める方法をぜひご活用ください。
この夏、合格への「ドア」を開けてみませんか?
第一ゼミナール 2025夏期講習会

小学生指導がパワーアップ!
最先端のAI&ICTの活用で最適な学習を提供

課題読書と自由読書の違いを知ろう
まずは、課題読書と自由読書の意味や違いについて確認していきましょう。
青少年読書感想文全国コンクールには、課題図書が対象の「課題読書」と、子どもが自由に本を選べる「自由読書」の2つの区分があります。
課題読書とは
課題読書とは、読書感想文コンクールの主催者が指定した本を読んで感想文を書く形式です。
本の専門家は毎年、新しく出版された本から子どもの学年による理解力に合わせて、子どもに感動を与えたり新しい知識を得られたりする書籍が選ばれます。
課題読書の内容は小説や実際にあった話、外国の作品を日本語訳したものなどさまざまです。
以下のように、学年ごとに分かれており、区分ごとに3~4冊用意しています。
- 小学校1・2年生
- 小学校3・4年生
- 小学校5・6年生
- 中学生
- 高校生
自由読書とは
自由読書とは、課題図書以外で読者が自分で読みたい本を選んで感想文を書く形式です。
ほとんどすべての本が自由読書となり、自分の感性に合わせて選ぶ・書くことができる点がメリットといえるでしょう。
ただし、青少年読書感想文全国コンクールによると、自由読書について以下のように説明されています。
教科書、副読本、読書会用テキスト類またはこれに準ずるもの、雑誌(別冊付録を含む)、パンフレット類、日本語以外で書かれた図書および課題図書は対象としません。ただし、課題図書であっても該当の部以外であれば、自由読書として応募することができます。
引用元:https://www.dokusyokansoubun.jp/youkou.html
つまり、教育現場で使われているものや、海外の言語で書かれた小説などは対象とならないので注意が必要です。
決め手は興味関心に合う「本選び」
よい読書感想文を書くには、よい読書体験が欠かせません。
「よい読書体験」とは、本を通じて心を動かされたり、自分を見つめなおしたり、わからなかったことが解決できたりすることだといわれます。
毎年発表される「課題図書」は、本の専門家の方々が、「子どもの興味や関心を引くかどうか」「多くの感動や知識が得られるかどうか」といった基準によって選ばれたものです。
本のプロが各学齢に合わせて厳選した「子どもにとってよい読書体験を得やすい本」ですから、それだけ読書感想文が書きやすい特徴を持つ本だといえるでしょう。
一方、「自由読書」には、お子さまの興味・関心に沿った本を選べるというメリットがあります。
読書感想文で高評価されるポイントのひとつが、「自分の体験や抱負を盛り込むこと」です。
例えば、野球をしているお子さまなら、野球選手の伝記を選ぶことで、自分自身の体験と重ねたり新たな気づきや心の動きなどが盛り込みやすくなったりすることで、イキイキとした読書感想文が書けるでしょう。
読書感想文は、お子さまが面白い本に出会い、読書の楽しさを知るチャンスです。
「課題図書か自由図書か」にこだわる必要はありません。「お子さまが楽しく読めそうかどうか」「お子さまが興味・関心を持てる要素があるかどうか」を基準に選びましょう。それが、読書感想文に対する評価にもつながります。
入賞しやすさに差はあるの?
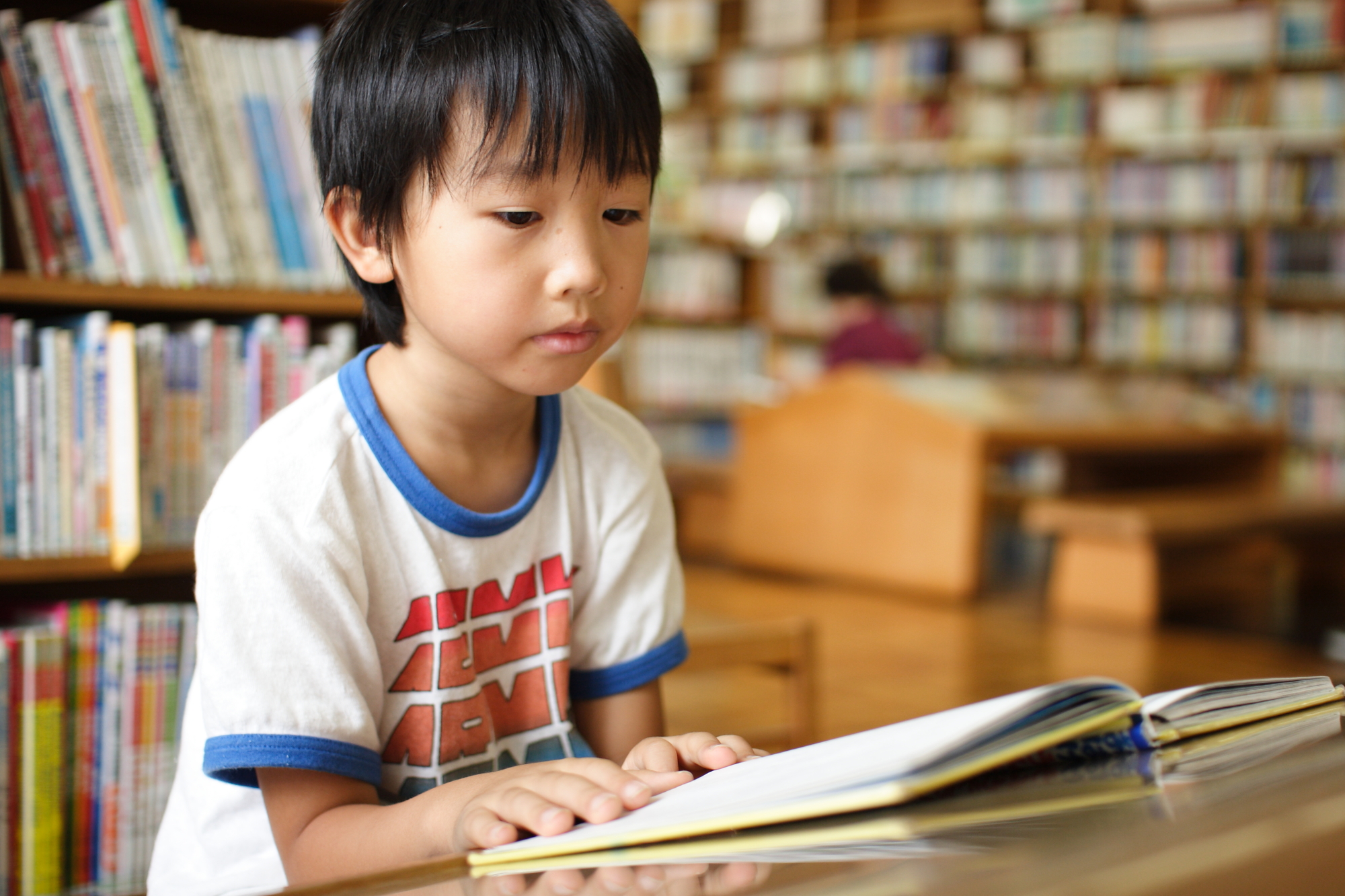
青少年読書感想文全国コンクールの審査は「地方審査→中央審査会」の2段階で行われます。
都道府県審査会では、学年別の部門ごとに「課題読書」と「自由読書」から1編ずつを選定するので、課題読書と自由読書の選ばれやすさは平等です。
なお、最終的な「最優秀作品」や「優秀作品」は、課題読書・自由読書を合わせた中から、決められた数だけ選ばれます。「最優秀作品」は、学年別部門ごとに、毎年1編のみ。
そこで、過去5年間に課題読書・自由読書から最優秀作品に選ばれた回数を調べてみました。
| 低学年 | 中学年 | 高学年 | 合計 |
|---|
| 課題読書 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 自由読書 | 3 | 3 | 1 | 7 |
小学校低学年・中学年・高学年の3部門の入賞者発表より
このように、5年間の最優秀作品については課題読書も自由読書も選ばれる数の差はほとんどありません。
「読書感想文は課題図書のほうが有利」ということではないため、お子さまが「書きたい」と思える、「書きやすい」と感じる本を選ぶとよいでしょう。
この夏、合格への「ドア」を開けてみませんか?
第一ゼミナール 2025夏期講習会

小学生指導がパワーアップ!
最先端のAI&ICTの活用で最適な学習を提供

読書感想文の構成と具体的な書き方
読書感想文は、やみくもに書き始めると最終的にまとまりのない内容になってしまいます。
感じたことを正しく書くためには、全体を通して伝えたいことをイメージできるように構成を作成することが重要でしょう。
ここでは、読書感想文の基本的な型である「四段落構成」とともに例文を紹介して解説します。
序論・オープニング
まずは、全体文字数の1割程度を目安に、本を選んだ理由や本を読む前の自分など、本と出会ったきっかけについて触れてみましょう。
特に、優れている読書感想文を書くには出だしが大事なので、読み手の興味をくすぐるオープニングをめざしましょう。
|
【例文】
毎週金曜日の午後7時、塾が終わると必ず駅前の横にある本屋に通りかかります。いつもなら何気なくスルーするのですが、その日はテストの結果が悪かったこともあり、参考書を探すために本屋に寄ることにしました。そこで、小学生ぐらいの子どもが楽しそうにサッカーをしている1冊の本に目が留まります。なんとなく手に取って読み進めていると、忘れかけていた小学校時代のクラブ活動の記憶が鮮明に蘇ってきます。
|
このように、「いつ」「どこで」「何を」「どのような感情で」の要素を入れることで、読者は自分と同じ立場で読み進めることができます。
あらすじ
続いて、簡潔にあらすじを書きましょう。
あらすじが長くなり、本の紹介文になってしまうこともあるため、できる限り簡潔にまとめることを意識しましょう。
【例文】
「○○〇」は、おとなしい性格のカズヤが、転入生のヒロシと出会って少しずつ成長していく物語です。
この本は、作者の「〇〇」が実際に体験した出来事をまとめたノンフィクション作品です。勉強ばかりの毎日に嫌気がさしていたことと、カズヤと私の状況が似ていたことで、カズヤを当時の自分に置き換えて読み進めていきます。 |
あらすじをまとめると同時に、次のステップである感想に自然な形で移れるように意識すると綺麗な構成となります。
感想
感想文のメインとなる部分で、全体文字数の6割程度を目安に書きます。
完全に読み終えてから感想を書くのは難しいので、本を読み進めると同時に「読書メモ」を書くことをおすすめします。
読書メモは「なぜ気になったのか」「どう感じたのか」を自分の気持ちを主体として書くようにしましょう。
【例文】
おとなしい性格のカズヤは活発な性格のヒロシと出会い、消極的なプレイをしていた弱い自分を打ち破り見事ハットトリックを決めます。その姿は、かつて私が転校生の〇〇と出会い、弱気な自分の殻を破り、キャプテンに任命されチームを県大会優勝に導いた時のことを鮮明に思い出させてくれました。 |
このように、本の内容に触れながら自分の気持ちを主体として書くと、より一層読者に感動を与えられます。
結論・まとめ
最後に全体文字数の2割程度でまとめを書きます。
まとめでは、本を読んで学んだことや気づいたこと、今後どのように活かしていくかなど書きましょう。
本をおすすめするわけではないので、「〇〇なので多くの人に読んでもらいたいです」といった内容は不要です。
【例文】
私は「〇〇」を読み、周りの人がどれだけ自分のことを考えてくれていて、ポジティブなエネルギーを与えてくれるかを理解することができました。
現在はサッカーという形ではありませんが、塾であの頃のように丁寧に指導してくれる〇〇先生や、成績が伸び悩んだ時に鼓舞してくれる〇〇くんの存在は、私にとってかけがえのない存在です。
しんどいこともたくさんある世の中ですが、両親や先生、友人などの身近な存在に対して感謝しながら、時には彼らの励みになれるように毎日を一生懸命に過ごしたいと思います。 |
本が自分にどのような影響を与えたかをまとめ、感想文を締めましょう。
小学生低学年向けの読書感想文の書き方のコツ
ここでは、読書感想文に苦手意識を持つ、小学生低学年のお子さまが楽しく読書感想文を書くコツについて解説します。
お子さまが読書感想文で頭を悩ませている場合には、以下の内容を参考にしてください
読む前の本の印象をメモ
読書を始める前に、「なぜこの本を選ぼうと思ったのか」や「表紙を見てどんな内容の本だと思ったか」などの質問をしてメモを取りましょう。
日常会話のように、学校であった楽しいことを共有することで、お子さまの「好き」や「興味」をそのまま引き出せます。
そして、本を読んだ後は「どんな話だった?」と尋ねてみましょう。
登場人物が誰で、どのような場所でどのように行動したかなど、物語の流れを思い出せるように質問することで感想文が書きやすくなります。
印象に残った文章やセリフ
読み進める中で、特に印象に残ったセリフがあれば、付箋を使ってページをマークし、気になった理由をメモしておきましょう。
お子さまがひとりで読み進めるのが難しい場合、一緒に読み進めるのもおすすめです。
また、低学年のお子さまは、気持ちを言葉にするのが難しいこともありますので、その場合は付箋だけでも問題ありません。
後で一緒にページを見返す際に、「どうしてこの部分が気になったの?」と理由を尋ねてみてください。
保護者の方も、お子さまと一緒に読む過程で、子どもの反応をメモすると良いでしょう。
登場人物になりきって想像する
お子さまが本を読み進めていく中で、「もしも自分が主人公ならどうする?」と、登場人物の目線でイメージさせましょう。
登場人物の目線で、感情が動かされた場面や印象に残った場面をメモしておくと書きやすくなります。
登場人物の立場になって同調することは、読書そのものを楽しむコツでもあります。
小さいうちからお子さまの想像力を発達させることは、読書感想文を書く技術を向上させるだけでなく、思考力や共感力、問題解決能力を育むことに繋がります。
感想文の苦手意識をなくす方法

一方で、興味のある本を選んで読んではみたものの、いざ作文用紙に向かうと何も書けない、となってしまう子がいます。もともと読書量が足りなくて、使える「言葉のひきだし」が少ないというのもありますが、大きな原因は別のところにあることも。
「内容から何か学んだことを盛り込みましょう」「前向きな感想を書きましょう」。書き方の丁寧な指導もないまま感想文を書きましょうと言われ、なんとかしぼり出した文章に、こんなふうにダメ出しされたら・・。大人でもペンが止まってしまいますよね。
こんな経験を何度か繰り返すうちに『読書感想文は苦手』の意識はすっかり定着してしまいます。今回はこの『読書感想文は苦手』の意識を白紙化するちょっとしたワザをご紹介します。
それは「感想文だから感想を書かなければいけない」と凝り固まっている思い込みの枠を外してあげる方法です。やり方はいたってシンプル。「読書感想文を書きましょう」といういつもの設問を「読んだ本を誰かに紹介する文章を書いてみよう」に置き換えるだけです。
紹介する相手は親しい関係の人がいいでしょう。お母さんでも友だちでも、お子さまが気兼ねなく話せるような相手なら誰でも構いません。紹介文ですから無理に感想を書く必要はありません。読んだ本の内容を気軽に話せる相手に自分の言葉で伝えるだけです。
それだったらできるかも!と感じた子どものペンは意外とすんなり動き始めます。最初は内容紹介と思って書き始めたとしても、親しい相手には本のいいところを伝えたくなるものです。書き終えるころには自然と読書感想文らしきものになっているでしょう。
完成したら、できるだけ良いところを見つけて褒めてあげましょう。何回かやるうちに苦手意識は雲散霧消していくはずです。
読書感想文の書き方に関するQ&A
最後に、読書感想文の書き方に関するよくある質問に回答いたします。
読書感想文の題名はどうやって決めたらいいのか?
実際に読み進めていく中で、最も感動したセリフや内容などを題名にすると良いでしょう。
高度なテクニックではありますが、読書感想文の結末で題名の内容に結びつく、題名の伏線を回収すると読み手に感動を与えます。
コンクールで受賞を目指すなら、読み手の興味を引く題名を考えましょう。
読書感想文の文字数に規定はあるのか?
文字数の規定はあります。
青少年読書感想文全国コンクールによると、文字数規定は以下の通りです。
- 小学校1・2年:800字以内
- 小学校3・4年:1,200字以内
- 小学校5・6年:1,200字以内
- 中学生:2,000字以内
- 高校生:2,000字以内
電子書籍を読んで書いてもいいのか?
紙媒体の書籍に限られているため、電子書籍は利用できません。
応募の際は、紙媒体の書籍を利用しましょう。
自分の学年と異なる課題図書でもいいのか?
問題ありません。
ただし、課題読書ではなく自由読書として扱われるので、自由読書の部として応募しましょう。
まとめ
この記事では、夏休みの読書感想文について解説しました。
夏休みの読書感想文には、読書感想文コンクールの主催者が決めた本を読んで書く「課題読書」と、自分で本を選んで書く「自由読書」があります。
どちらを選ぶにしろ、大切なのはお子さまが心から興味を持つ本を選ぶことです。
課題図書はプロが選定した質の高い書籍であり、感想文の素材として優れています。自由図書は個々の興味に沿った選書ができるため、お子さまが自分の体験や感情を盛り込みやすいでしょう。
また、読書感想文はお子さまにとって苦手意識を感じやすいですが、本を読んで感じた体験を人に伝える良い機会でもあります。感想文を書こうとする前に、「本を誰かに紹介する」という意識を持つことで、自然と文章が書きやすくなります。
もし、お子さまが読書感想文に対してネガティブなイメージを持っている場合は、読んだ本の登場人物や印象に残った場面などを質問して、会話形式で楽しく取り組めるように工夫してあげてください。感想文を書くプロセスを楽しむことで、読書の楽しさも再発見できるでしょう。
いよいよ夏休み。ぜひこの記事を参考に、お子さまにとっての「最高の一冊」と出会い、読書感想文を楽しく仕上げてみてください。