部活や課外活動、習い事、友達との遊び……中学生には、やりたいこと、やらなければならないことがたくさんあります。
そんな忙しい中学生が、学習効果を上げるには「同じ時間内でいかに効率の良い学習をするか」ということがカギとなります。
その際に実践したいのが、脳の性質、特に「記憶の仕組み」を活かした学習です。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

学習効率アップのカギ:「初頭効果」と「新近効果」とは?

記憶の仕組みを活かした学習を行う際のキーワードとなるのが、「初頭効果」と「新近効果」です。
初頭効果とは、物事の最初は記憶に残りやすいという効果。これに対して新近効果とは、物事の最後は記憶に残りやすいという効果を指します。これらは心理学の分野で用いられる言葉のため、一般的にはあまり馴染みがないかもしれませんが、次の例を想像していただければわかりやすいのではないでしょうか。
「コーヒー、犬、りんご、道路、パソコン、ジュース、ピアノ、鉛筆、財布、山……」といった脈略なく並べられた複数の単語を暗記するとしましょう。このような場合、正解率が高いのは最初と最後の単語で、真ん中に出てきた単語はあまり覚えられないといわれています。
では、どうしてこのような結果になるのでしょうか。その理由としてカギとなるのが、「短期記憶」と「長期記憶」という2つの記憶段階です。
暗記の正解率には、「記憶の段階」が関係している!
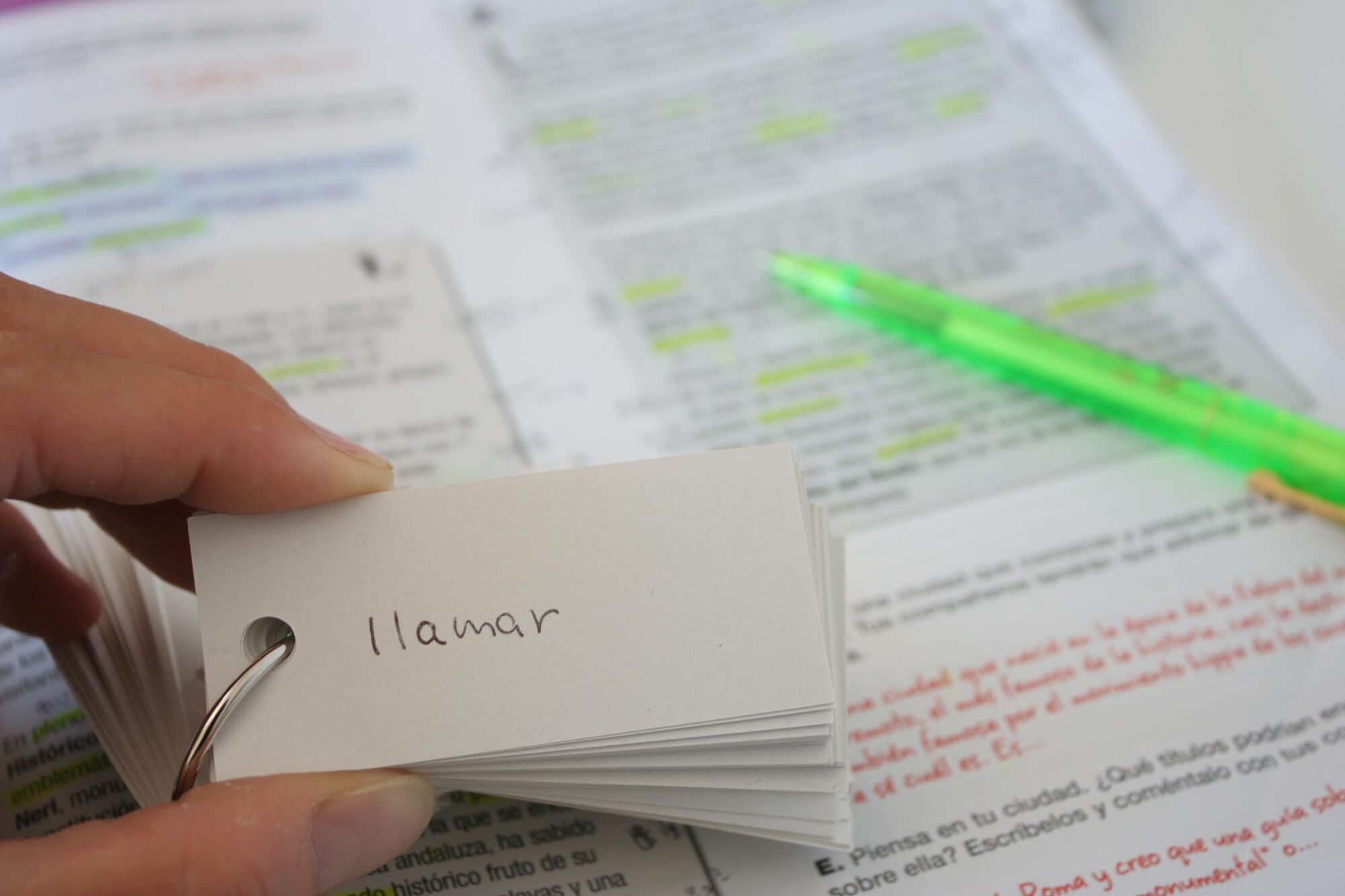
人の記憶には、短期記憶と長期記憶が存在します。
短期記憶とは、その名の通り短期的に保持される記憶のこと。例えば、「今聞いた電話番号を忘れないように復唱したり、頭の中で繰り返したりすることによって保持している」というような場合がこれにあたります。
短期記憶が保持される期間は人によって異なりますが、一般的には数秒から数分といわれ、情報の繰り返しを中断したり、他の情報が入ってきたりするとサッと消えてしまうともいわれています。
これに対して長期記憶とは、長期的・永続的に保持される記憶のこと。例えば、「何度も電話を掛けている自宅や実家の電話番号をずっと覚えている」といった例がこれにあたり、最初の段階では短期記憶として保持された情報が、繰り返し想起されることで長期記憶へと変化したということです。
さて、ここで先述した初頭効果と新近効果の話に戻りましょう。
最初に挙げた複数の単語を暗記する際、ほとんどの人は頭の中で単語を復唱するでしょう。その場合、最初に出てきた単語は記憶に残りやすくなるという位置効果があります。また、最初に出てきた単語は自然と繰り返される頻度が高くなるため、短期記憶から長期記憶へと移行しやすくもなるといわれています。
一方、最後に出てきた単語が覚えやすいというのは、直前に覚えたものだから記憶に残っているという簡単な原理が理由だといわれています。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

初頭効果と新近効果を活かして、効率的な学習を

初頭効果と新近効果は、学習効率アップのために活かすことができます。つまり、「最初」と「最後」を「多く作り出す」ことによって、脳に情報を記憶させやすくするのです。
例えば、学習する時間を細かく区切って適度に休憩を入れるという方法を行ってみましょう。そうすれば、おのずと「最初」と「最後」が多くなります。学校や塾の授業が50分~60分で一区切りになっているのには、こういった理由もあるようです。
もっとも、自宅での勉強、特に受験勉強や試験勉強となると、学校や塾のようにきちんと区切りをしない子どもが多いのではないでしょうか。このような勉強スタイルは、記憶の仕組みの観点からみると決して効率的だとはいえません。また、集中力が落ちる原因にもなってしまいます。
お子さんが長時間続けて勉強机に向かっていたら、適度な休憩をとるようにアドバイスしましょう。
もうひとつ、順番を変えて学習を行うというのも良い方法です。例えば、参考書を使って学習する場合には、いつも同じ順番に学習を進めるのではなく、たまには真ん中あたりの章から始めてみたり、最後に真ん中部分を持ってきたりしてみましょう。ちょっとした工夫で、学習効率の向上が期待できます。
いかがでしたか。記憶の仕組みを活用した学習効率アップ方法、ぜひお子さんにも教えてあげてくださいね。