新学習指導要領に沿って大きく改訂された中学校教科書が、いよいよ2021年4月から導入開始となります。従来の基礎的な知識・技能重視型から、思考力・判断力・表現力に加えて自分から学習に取り組む姿勢を重視する方向に大きく舵を切った今回の教科書改訂。
今回は、改訂された新教科書がこれまでの旧教科書とどう違っているのか、またそれによって子どもたちの学びはどう変わるのかを見ていきます。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

英語の難易度が大幅アップ!単語が2倍に?
新教科書になって質・量ともに大幅にボリュームアップする教科が英語です。今回の改定の最大の特徴と言ってもいいでしょう。
例えば単語は、小学校で学習済み(とされている)基礎的な600~700語は別にして、ここから新たに1600~1800語ほどの新出語を中学校3年間で学習することになります。新旧教科書別の単語取り扱い数を比べてみても、「NEW HORIZON」で22%増、「NEW CROWN」で45%増など、その差は明らか。小学校の単語数も含めると中学卒業までに学習する単語は、従来の約2倍になります。
文法でも、従来は高校内容の定番だった現在完了進行形や仮定法などが、中学校の履修内容に下りてきているなどの難化が見られます。
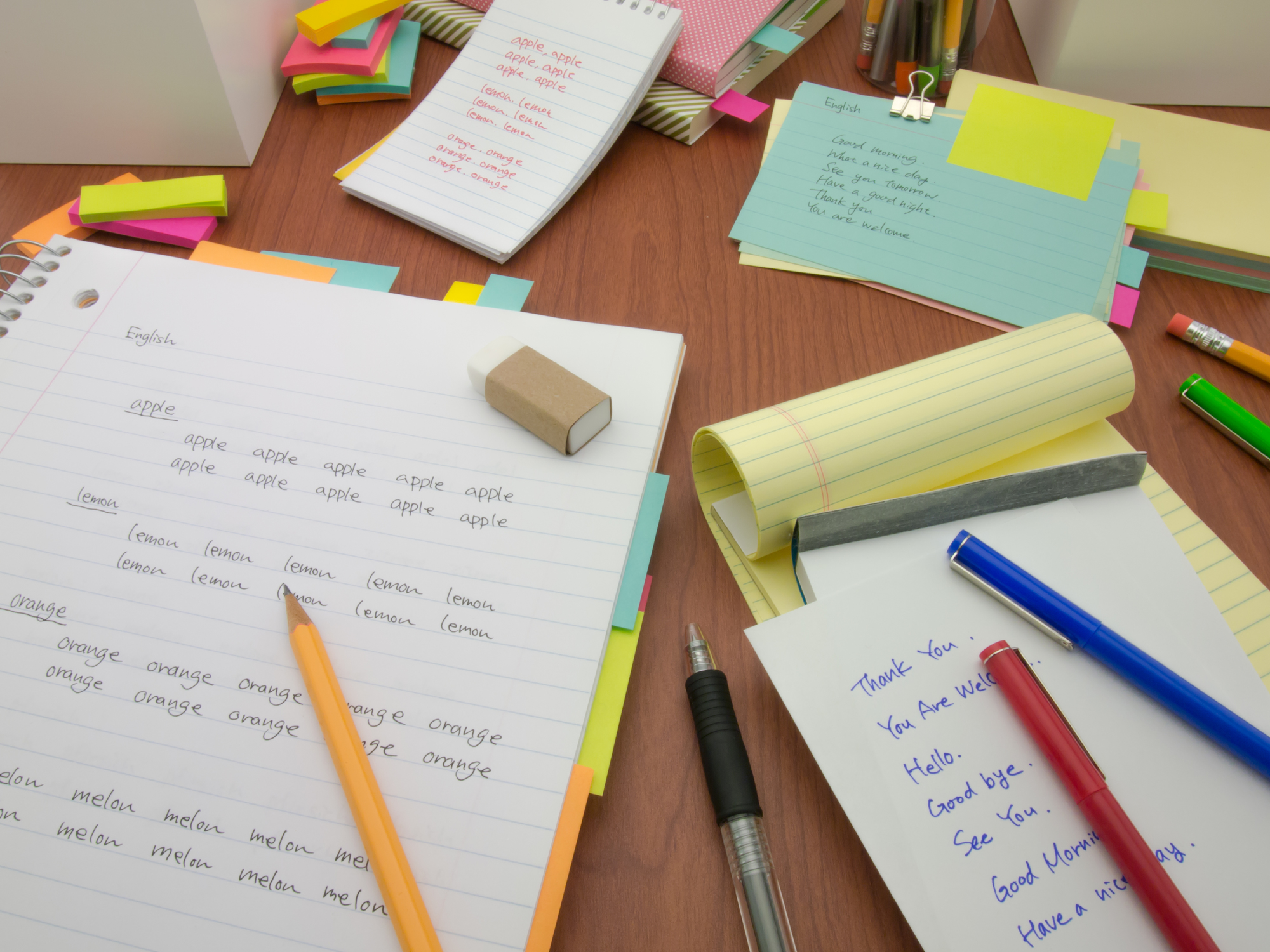
これだけではありません。環境や気候変動、教育、食料、水など様々な地球規模の問題を解決するための「国際社会共通の目標」(※1:SDGs)をトピックにした内容を多く採用。
これまでの「英語を学ぶ」から「英語で学ぶ」(※2:CLIL)へのシフトを強く打ち出しているのも大きな特徴です。ただ英文を読んで書かれている意味を理解できればそれなりに何とかなっていた従来の勉強法では通用しなくなるのは明らかです。
例えば「NEW HORIZON」は、2016年にアメリカのオバマ大統領が現職の大統領として初めて広島を訪れた話題を取り上げ、下記の英文のように評しています。
It meant a lot to the city, to Japan, and to the world.
世界大戦当時の日米関係、唯一の被爆国、現代社会における核兵器の位置づけ、戦後71年間も現職のアメリカ大統領が被爆地訪問をしなかった理由など、本文では一切触れられない背景についての予備知識がなければ、「It meant a lot」が示す意味を理解することはできないような構成。
ほかにも理科の履修範囲である食物連鎖を取り上げる英語の教科書があるなど、教科横断型の内容が大幅に増え、「英語で学ぶ」の方向性が鮮明になっています。これまで以上に総合的な学力が求められることになるでしょう。
また、授業の原則英語化、英語4技能のバランスのとれた習得、実際のコミュニケーションで活かせる文法・語法の重点学習などの方針も打ち出されています。これまで読み書き中心だった英語学習の方法にも、新学習指導要領は大きな変化を求めているのです。
受験を控える新中3生は負担大
英語の新教科書は、新出単語の量・難度とも飛躍的にアップします。特に新中3生は、旧指導要領では学習していないにも関わらず、新指導要領では1・2年時にすでに学習したことになっている単語や文法が多数出てくることになります。
学習塾などでそれを補えれば、ついていくことができるでしょうが、学校だけではおそらく太刀打ちできないでしょう。授業が進むほどに分からないことが雪だるま式に増えていき、授業運営自体が立ち行かなくなる学校も出てくるのではと危惧されています。
リーディングは「英語で学ぶ」ための抽象度が高いテーマが多く扱われています。英語力もさることながら、一般社会常識や論理的思考力も問われることになります。
さらに、これらの抽象度が高いテーマに対して、発表やディベートなどの「活用」に重点が置かれているため、基本的な単語や文法知識の運用練習に割く時間が取れずに、習得は生徒任せになりやすい構成だということに留意が必要です。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!


保護者のみなさんはお子様が新しい教科書を受け取ってきたら、少し時間を取って内容を確認してみてください。ご自身が中学生だった頃と大きく変わっていることに気がつくはずです。特に、思考力・判断力・表現力の3つをどんなアプローチで身につけさせようとしているかという視点で見てみると、今と昔の学びの変化が実感できるでしょう。
ただし注意が必要なのは、身につけるべき力が変化しても知識の習得が不要になるわけではないという点です。知識が足りていないと、思考の土台が強固ではないため、比較したり共通点を見つけ出したりすることが難しいでしょう。
「環境保全と経済発展の両立に必要なことは何だろう」
「生物を絶滅から守るために何ができるだろう」
例えば、これらの問いに対する課題解決策を出すためには、多くの知識を土台にした多面的な見方や様々なものと関連づけての検討、論拠や意見を明確にして表現することが必要になります。つまり知識が足りないと、第一歩からつまずくということです。
今回の新学習指導要領は、高校・大学への「接続」が重視されています。中学校の学習内容に学び残しやつまずきがあると、後々の学びにも影響してしまいます。学校での学習だけでは厳しい部分が出てきますので、模試や塾を上手に活用してお子様の学習状況をしっかり見守ることの重要度は今後、ますます高まっていくでしょう。
第一ゼミナールは新学習指導要領への移行に合わせて、2021年3月から英語指導を強化し、学習法をバージョンアップします。例えば英単語1つをとっても、目だけでなく耳や口も使う「クイックレスポンス方式」で身につけることで、単語訳が九九のように出てくるようになります。さらに、学んだ単語をテキストの文法で使い、実際に外国人講師とのレッスンで使うことで、知識としてだけ身につけるのではなく、「一生自分のものとして使える英単語」として身につきます。
保護者説明会や無料体験にご参加いただき、これまでとは一線を画す「試験対策だけにとどまらない、実際に使えるようになるための第一ゼミの英語指導」をご確認ください。
※1:SDGs
「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称であり、2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた、国際社会共通の目標。
※2:CLIL
「Content and Language Integrated Learning」の略称。教科科目やテーマの内容(content)の学習と外国語(language)の学習を組み合わせた学習(指導)の総称で、「内容言語統合型学習」などと訳される。主に英語を通して、何かのテーマや他の教科等を学ぶ学習形態をこう呼ぶことが多い。