「DXハイスクールって何だろう?」
「具体的にどのような取り組みをしているの?」
「SSHやリーディングDXスクールとは何が違うの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
DXハイスクールは、文部科学省が推進するデジタル人材育成のための新たな教育施策です。情報や数学を重視したカリキュラムを基盤に、ICTを活用した文理融合型の学びや探究活動を通じて、次世代を担う人材の育成を目指しています。
この記事では、DXハイスクールの目的や実施内容、他の教育施策との違いについて詳しく解説します。デジタル教育に関心のある方は、ぜひ最後までお読みください。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

DXハイスクールとは
DXハイスクール(高等学校DX加速化推進事業)は、文部科学省が主導する教育支援事業で、2024年度からスタートしました。
※DXとは、デジタル・トランスフォーメーションの略でデジタル(IT)技術を活用し社会や生活の形・スタイルを変えることを指します。
あらゆる分野においてデジタル技術が求められる現状に対応するためは、デジタル技術を使いこなせる人材を増やすことが必要不可欠です。
そのため、文部科学省は、情報・数学教育を重視するなどの条件を満たした学校に対し、デジタル教育をするための経費を支援しています。
なお、初年度の2024年度は1,010校がDXハイスクールに採択されました。
DXハイスクール事業の目的

DXハイスクールは、急速に進むデジタル社会に対応できる人材を育成するための教育施策で、主に2つの目的があります。
目的1:デジタル人材の不足に対応するため
経済産業省の「IT人材受給に関する調査」の中で、2030年にはIT人材が最大78.7万人不足する恐れがあると発表されています。
この状況に対応するため、文部科学省は、大学教育段階における自然科学(理系)分野の学生割合を5割にすることを目標とし、目標達成のために、理系学部の新設など、さまざまな政策を進めています。
その取り組みの成果を最大限に発揮するために、高校教育段階から、デジタルに強い人材を育成することを目的として、この事業が開始されました。
目的2:文理横断的・探究的な学びを推進するため
現代の社会では、単に知識を詰め込むだけではなく、自ら考え、課題を探求し解決する力が必要とされています。
内閣の下に設置された教育政策に関する会議である「教育未来創造会議」の中で、「予測不可能な時代に必要な文理の壁を超えた普遍的知識・能力を備えた人材育成」を目指すと提言されました。
参照:https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/mirai_jinzai/pdf/005_s01_00.pdf
しかし、多くの高校では早い段階から文系コースと理系コースに分けられ、選択したコース以外の教科の学びが不十分になる傾向があるのが現状です。
このような事態に対応するため、DXハイスクールは、文理横断的・探究的な学びを通じて、多様なスキルを持った人材を育成することを目指しています。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

DXハイスクールの具体的な取り組み内容
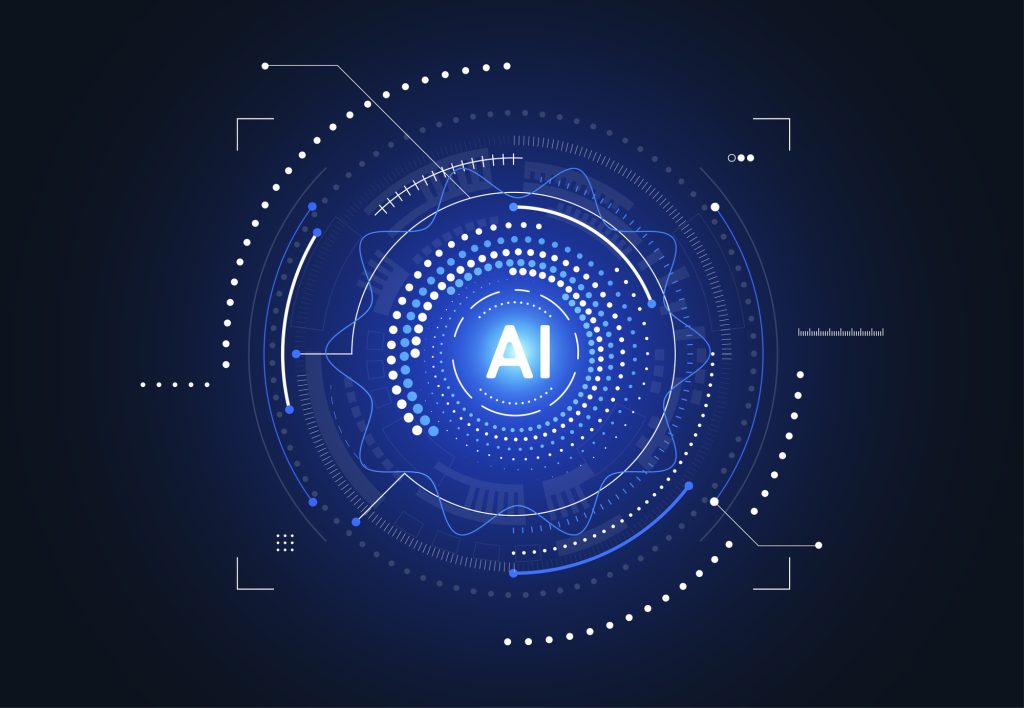
DXハイスクールとして採択された高校では、次世代のデジタル人材を育成するために、さまざまな取り組みをしています。
情報Ⅱなどの教科・科目の開設
DXハイスクールでは、従来の情報科目に加え、「情報Ⅱ」などの専門的な科目が新たに開設されます。
情報Ⅱでは、プログラミングの基礎やデータの扱い、AIの活用方法など、現代のデジタル社会において必要とされる知識と技術を学べます。
また、数学や理科と組み合わせたカリキュラムを編成することで、データ活用の基礎から応用までを体系的に学べる仕組みが整えられています。
デジタル環境の整備と教育内容の充実
デジタル教育を推進するためには、学習環境の整備が不可欠です。
DXハイスクールでは、生徒が自由にプログラミングやデータ分析を学べるよう、最新のICT機器や高速インターネット環境の整備を進めています。
具体的には、ハイスペックPCや3Dプリンタの導入に加え、大学の教員や学生による実習の実施など、実践的な学びを支援する取り組みが行われています。
実施の取り組み例として、大阪府立枚方津田高等学校では、大阪成蹊大学データサイエンス学部の教授を招き、高大連携授業が開催されました。
参照:https://www.osaka-c.ed.jp/blog/hirakatatsuda/tudanews/2025/01/15-274705.html
学科やコースの新設
DX人材を育成するため、一部の高校では「情報科学科」や「データサイエンスコース」など、専門的な学びができる学科やコースが新設されています。
これにより、生徒は従来の普通科では学べなかった高度なデジタル技術を体系的に学習できるようになります。
たとえば、大阪府立園芸高等学校では、学校設定選択専門科目として「サイエンス情報」が復活します。
参照:https://osaka-engei.ed.jp/information/page-17664/
上記3点以外にも幅広い活動が行われていますが、その内容は高校によって異なるため、各高校のサイトなどで、どのような取り組みが行われているのか確認してみてください。
DXハイスクールの採択状況
2025年度におけるDXハイスクール事業では、1,191校が採択校となりました。
下表は、関西地域2府4県の採択校数をまとめたものです。
| 採択校数 |
| 公立 | 私立 | 合計 |
| 大阪府 | 47 | 20 | 67 |
| 兵庫県 | 41 | 17 | 58 |
| 京都府 | 25 | 14 | 39 |
| 奈良県 | 11 | 3 | 14 |
| 滋賀県 | 10 | 3 | 13 |
| 和歌山県 | 12 | 1 | 13 |
参照:文部科学省「令和7年度高等学校 DX 加速化推進事業(DX ハイスクール)」の採択校をお知らせします」
DXハイスクールと他のデジタル教育施策との違い

現在、DXハイスクール以外にも、さまざまなデジタル教育施策が行われています。それぞれの施策には特徴があり、DXハイスクールとは異なる目的や対象が設定されています。
以下に、代表的な施策との違いを紹介します。
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)
スーパーサイエンスハイスクール(SSH)とは、科学技術・理科・数学教育を重点的に行う文部科学省指定の高校を指します。
SSHは理科や数学を中心とした高度な科学技術教育を推進し、国際的に活躍できる科学技術人材の育成を目的としています。一方、DXハイスクールはデジタル技術の学びを重視しており、幅広い分野で活用できるデジタル人材の育成を目指しています。
SSHが科学技術分野の研究や実験に重点を置くのに対し、DXハイスクールは、情報技術やデータ活用を基盤とした学びを提供する点が大きな違いです。
リーディングDXスクール
リーディングDXスクールは、文部科学省が推進する小・中・高校を対象としたデジタル教育の取り組みで、全国の約200校が指定校となっています。
この施策では、GIGAスクール構想によって整備された「1人1台端末」と「クラウド環境」を活用し、学校教育におけるデジタル化を加速させることを目的としています。一方、DXハイスクールは、高等学校を対象とし、デジタルなどの成長分野の人材育成に重点を置いています。
このように、リーディングDXスクールが教育全体のデジタル化を推進するのに対し、DXハイスクールは、特にデジタル技術を専門的に学ぶ環境を整備し、未来の産業を支える人材を育成する点が大きな違いといえるでしょう。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

まとめ
DXハイスクールは、文部科学省が主導する「高等学校DX加速化推進事業」の一環として実施されている教育施策です。
この事業では、情報や数学を重視した教育カリキュラムの充実、ICTを活用した文理横断型・探究型学習の推進などを通じて、次世代のデジタル人材の育成を目指しています。社会のDX化が進む中で、デジタルスキルを持つ人材の需要はますます高まっており、DXハイスクールでの学びは将来的に大きな強みとなるでしょう。
お子さまがDXハイスクールに興味を持った際には、採択された高校の取り組みやカリキュラムを調べ、どのような学びができるのかを確認することをおすすめします。
さまざまな選択肢を比較し、お子さまに最適な環境を見つけることで、将来のキャリア形成にもつながる有意義な教育の機会を得られるでしょう。