「普段は塾に通っていないけど、夏休み中だけでも塾の夏期講習に参加させたい」と考えるご家庭も多いのではないでしょうか。
夏休み中ずっと遊んでいると、学習習慣が乱れたり、勉強に対するモチベーションが下がったりしやすい時期です。周囲のお子さまが塾で頑張っている様子を見ると、「うちの子だけ置いていかれそう」と不安になる保護者の方も多いはず。
そもそも夏期講習だけ塾に通うことができるのか。疑問に思う人もいるでしょう。
この記事では、夏期講習のメリットやデメリット、さらに夏期講習を受講する際の注意点を解説します。
この夏、合格への「ドア」を開けてみませんか?
第一ゼミナール 2025夏期講習会

塾の夏期講習だけを受けることは可能!
多くの塾では、夏期講習だけの受講が可能です。
ただし、なかには塾に通っている生徒だけが受講する前提の夏期講習もありますので、検討している塾の資料を取り寄せたり、問い合わせをしたりして参加できる塾を探しましょう。
夏期講習を受けるメリット7選
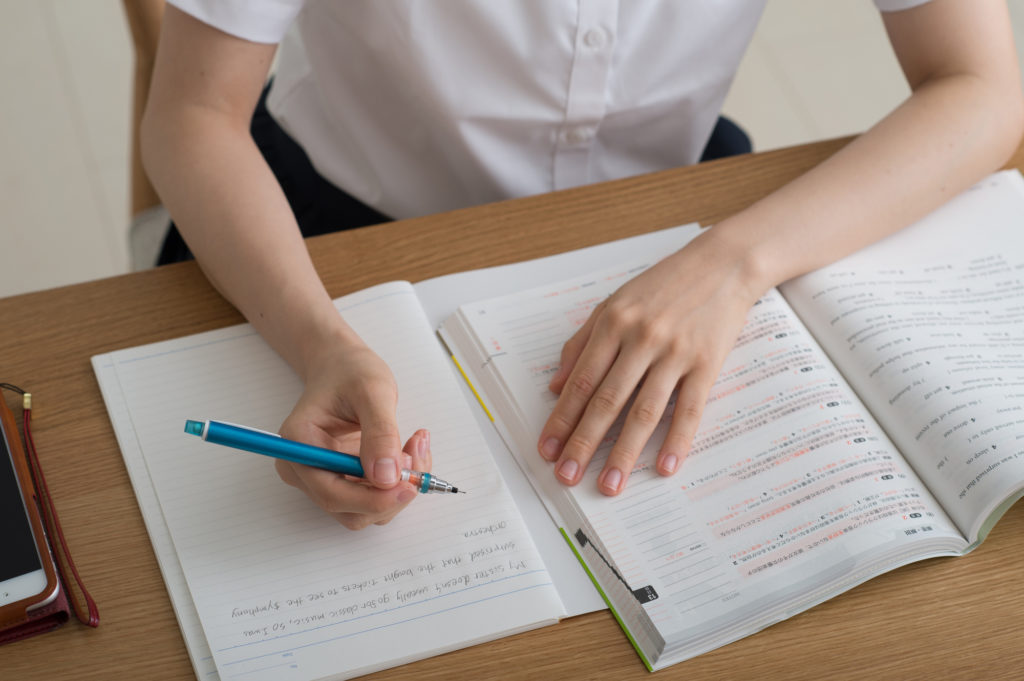
夏期講習を受けるメリットは、以下の7つです。
- 学習習慣を維持できる
- 苦手科目をしっかり強化できる
- 勉強のコツや学習ノウハウが身につく
- 学習内容を総復習できる
- 入会金割引など、特典が付く場合が多い
- 授業以外でも塾を利用できる
- 自分の実力を把握できる
それぞれを詳しく解説します。
学習習慣を維持できる
夏休みはおよそ1カ月半あります。塾に通っていなければ、その期間の勉強は学校の宿題程度で済ませるケースも少なくありません。
しかし、夏期講習に通えば学習習慣を維持して休み期間を過ごすことができ、学力低下を防ぐこともできるでしょう。塾によっては宿題の進捗状況を管理してくれるので、効率よく勉強に取り組むことができることもメリットです
苦手科目をしっかり強化できる
勉強する科目や授業のコマ数を選べる塾が多いことも夏期講習のメリットです。
普段の授業では1つの科目を週に1~2回受けることが一般的ですが、夏期講習では苦手な科目を短期的に集中して勉強することで、苦手科目を強化できるでしょう。
苦手科目の克服だけではなく得意な科目をより伸ばすことも可能ですし、自分のニーズに合った学習カリキュラムを組むことができます。夏休みを有効に使ってお子さまの成績向上につなげましょう。
勉強のコツや学習ノウハウが身につく
学校では知識などの「学習内容」は教わりますが、「勉強方法」まで教えてくれる先生は意外と少ないものです。
塾に行くことで、学校では教えてもらえない勉強のコツや、教科書に載っていない解き方を指導してくれるため、自己流では身につけにくい勉強スキルが得られます。夏期講習の短期間でも、正しい学習法が身につくことでしょう。
学習内容を総復習できる
夏期講習では、これまでの学習内容を単元ごとに復習できるカリキュラムが用意されていることが多いです。
学校の授業では見落としてしまった内容や理解が曖昧だった単元にも気づきやすく、抜け漏れの確認にも効果的です。テストでよく出る頻出テーマに絞って復習できるケースもあるため、実力アップにつながる効率的な学習機会となるでしょう。
特に受験を控えた中学生にとっては、基礎固めの絶好の機会となります。夏期講習を通じて、学習内容を総合的に振り返ることで、夏期講習以降の学習や入試対策にも自信を持って取り組めるようになるでしょう
入会金割引など、特典が付く場合が多い
夏期講習を受講すると、そのまま通塾する際に入会金が割引されるなど、特典が受けられるケースが多くあります。
「まずは講習だけ」という方にとっても費用を抑えてスタートしやすい時期です。キャンペーンの内容は塾によって異なるので、検討している塾の夏期講習の特典を調べてみると良いでしょう。
授業以外でも塾を利用できる
夏期講習だけの受講生だとしても、その期間は立派な塾生です。その間は授業を受けられることはもちろん、授業以外の形でも塾を利用できるのは、夏期講習のメリットです。
なかでも自習室が使える塾であればこれを利用しない手はありません。夏の暑い日に、静かで涼しく集中して勉強できる塾の自習室は非常に良い環境です。夏期講習を受ける塾を選ぶ際は、制限なく自習室が使えるのか把握しておきましょう。無料で使えるかどうかはもちろん、席数が十分か、授業がない日も使えるかなども確認しておきましょう。
自習室の利用だけでなく、講師にわからない問題の質問をしたり、置いてある問題集や参考書を使ったりと、授業以外でも活用できるシーンが多くあることでしょう。
自分の実力を把握できる
集団授業や塾内模試を通じて、お子さまは自分と周りとの実力を把握できることも夏期講習を受講するメリットです。
授業で講師から問題を尋ねられた時の受け答えの様子や塾内模試の成績などで、お子さまは現在の自分の実力を身をもって感じることができます。
周りの生徒とのレベルの差を実感すると危機感が生まれ、勉強のモチベーションが上がることが期待できます。自分の実力を早い段階で客観的に把握できれば、この先の受験に活かすことができるでしょう。
この夏、合格への「ドア」を開けてみませんか?
第一ゼミナール 2025夏期講習会

夏期講習を受けるデメリットと注意点

一方で、夏期講習にも以下のようなデメリットがあります。
- まとまった費用が必要
- 夏休み明けのテストへの期待が大きくなりすぎる
- 学校の宿題に塾の宿題が加わり、お子さまの負担が増える
お子さまだけではなく保護者の方にとっても不都合がないかを確認しておきましょう。
まとまった費用が必要
夏期講習の費用は指導形態によっても異なります。また、受講するコマ数を増やしたり特別講座を申し込んだりするとさらに費用がかかる可能性もあります。
夏期講習を受けるには、ある程度のお金が必要だと理解しておきましょう。ただし、無料や割引を実施する塾もあるため、検討している塾の情報をチェックしておきましょう。
夏休み明けのテストへの期待が大きくなりすぎる
夏期講習を受ければ成績が上がるだろう、と考えるのはいたって当然のことです。しかし、成績はすぐに上がるものではなく、特に勉強が苦手だったお子さまに関してはなおさら簡単ではありません。
成績を上げるためには、基礎学力を身に着ける段階から取り組む必要があります。ただし、基礎学力は短期間だけでは身につきにくい点に注意が必要です。
その結果、成長はしているのにテストの成績は上がらないといった事態も考えられます。お子さまの状況によっては、夏期講習だけでは目に見える結果が出ない可能性があることを前もって認識しておきましょう。
学校の宿題に塾の宿題が加わり、お子さまの負担が増える
普段通塾していないお子さまにとっては、夏休みの宿題に加えて塾の宿題が出されて、勉強の負担が急増することになります。
その反動で夏期講習が終わってから勉強を全くやらなくなってしまう恐れもありますし、勉強への苦手意識が強くなってしまうこともあるでしょう。
個別指導塾であれば、お子さまの普段の勉強習慣を塾に伝え、宿題の量を調節してもらえることもあるので事前に確認しておきましょう。
夏期講習だけでも、受けてみる価値あり!

ここまで、夏期講習を受けるメリット・デメリットを解説しました。これらを比較しても夏期講習は受けるメリットが大きいと考えられます。
デメリットを差し引いても夏期講習はメリットが大きい!
夏期講習を受講するデメリットを挙げましたが、それらを予め知っておけば、対処可能です。対して受講するメリットは大きく、塾に通わないと得られないものばかりです。
夏期講習を受講して勉強のコツやポイントを押さえて学習する習慣を身につけることができれば、お子さまにとって役立つ財産となるでしょう。
また夏期講習に参加すると、学校で普段顔を合わせている友達よりも、意識が高い仲間に会うことができます。高い目標を持つ仲間と一緒に勉強することで刺激になりますし、見違えるほど真摯に勉強に励むようになるお子さまもいます。夏期講習を受講するメリットは想像以上に大きいのです。
良い塾に出会えれば、そのまま継続しても良い
塾の指導方針や授業形態、講師のレベルなど、お子さまが実際に授業を受けて「普段から通いたい・通わせたい塾」だと感じたなら、そのまま継続して通わせることができるのも夏期講習の良いところです。
良い塾の条件は様々ですが見分けるポイントとして分かりやすいのは「お子さまが嫌がらずに塾に行くか」です。
そもそもお子さまにとって、塾はあまり行きたくない所。勉強が苦手な子であればなおさらです。それにも関わらず嫌がらないで塾に行けるということは、塾での勉強が楽しいと感じている可能性が高いです。
そんな塾に出会えたならば、夏期講習だけの受講ではもったいないと考えられます。お子さまの意見を聞きながら引き続きの通塾を検討しましょう。
夏期講習を受ける前に知っておきたい5つの注意点

ここからは、夏期講習を受けるときの5つの注意点を解説します。
- 「夏期完結型」か「通常授業の延長型」かを確認する
- 料金や授業内容、スケジュールを事前に調べておく
- お子さまの負担になり得る宿題の量かどうかを確認しておく
- 申し込みは余裕をもって行う
- 夏期講習を受ける目的を明確にし、お子さまと共有しておく
これらを把握しておけば、夏期講習での失敗を少なくできますので、詳しくチェックしていきましょう。
「夏期完結型」か「通常授業の延長型」かを確認する
主に集団塾の夏期講習は「夏期完結型」と「通常授業の延長型」の2つに分けられます。「夏期完結型」は、文字通り夏期講習で学習内容が完結する講習のことです。
一方「通常授業の延長型」は、塾生が夏休み前から受けている授業の続きを夏期講習として行う講習のことです。
通常授業の延長型の夏期講習は、それまで塾の授業を受けていることが前提として進むので、今まで塾に通っていなかったお子さまは授業についていけなくなる恐れがあります。
はじめて塾に通う場合は「夏期完結型」の講習をおすすめします。
料金や授業内容、スケジュールを事前に調べておく
夏期講習を申し込む前に、受講料金や授業内容、日程は必ず調べておきましょう。これらは塾によって異なるので、検討している塾のホームページのチェックや説明会に参加する、または直接問い合わせて確認してください。
特に夏休み中、家族旅行などの予定が入っていたり、お子さまの習い事や部活動が忙しかったりする場合は授業のスケジュール確認は必須です。授業が予定と重なる場合は、補講でどれぐらい柔軟に対応してもらえるか確認しておくと良いでしょう。
お子さまの負担になり得る宿題の量かどうかを確認しておく
夏期講習では授業以外にも宿題が出されることが多く、その量や難易度は塾によって大きく異なります。なかには、毎回の授業ごとに課題が出され、家庭学習の時間がかなり必要になるケースもあるため、注意しましょう。
部活動や家庭での予定、学校の宿題とのバランスを考えたうえで、夏期講習の宿題が無理のない範囲かどうかを事前に確認しておきましょう。特に長時間の勉強に慣れていないお子さまにとっては、宿題の多さがストレスとなり、かえって学習意欲を下げてしまうこともあります。
説明会や体験授業の際に宿題の具体的な量や内容を尋ねることで、イメージがしやすくなります。無理なく取り組める学習量であるかを見極め、夏期講習を有意義なものにしましょう。
申し込みは余裕をもって行う
夏期講習には余裕をもって申し込みましょう。人気の塾であればあるほど、定員はすぐに埋まります。早ければ6月上旬から申し込みが開始する塾もあるので、それ以前から塾の資料を取り寄せておきましょう。
行かせたい塾の夏期講習の募集が締め切ってしまったせいで、遠くの塾に行くことになる恐れもあります。もしお子さまが受験生ならば、夏休みを満足に勉強できないのは致命的です。
そうならないように夏期講習の受講は早めに行動をとる必要があります。できれば早めに夏期講習に参加させるかどうかを決めて、どの塾に申し込むのか、いつから申し込みが始まるのかなど把握して、余裕を持って動きましょう。
夏期講習を受ける目的を明確にし、お子さまと共有しておく
夏期講習は、受講する目的を明確にしておき、その目的はお子さまと共有しておきましょう。何も意識せず漫然と授業を受けてしまうと、勉強に身が入らず学習効率が下がってしまう可能性があります。
目的の例としては、「基本レベルの計算、特に分数の計算を克服する」や「英単語が苦手なので、単語の覚え方を教わる」、「基本レベルの勉強はできるので、応用問題をたくさん解く」などです。お子さまの学力や得意不得意を基に考えましょう。
何を目的にすれば良いか分からない場合、塾の面談で相談するのがオススメです。お子さまに合わせた目標や、受講プランを考えてくれるはずです。もし仮に対応が良くないと感じたなら、迷わず他の塾を検討しましょう。積極的に塾を利用する気持ちで臨むことが大切です。
この夏、合格への「ドア」を開けてみませんか?
第一ゼミナール 2025夏期講習会

夏期講習に関するよくあるQ&A
最後に、夏期講習に関するよくある質問をご紹介します。
夏期講習の平均的な費用は?
夏期講習の費用は、塾の種類(個別指導・集団指導)や地域、学年、受講する教科数やコマ数によって大きく異なります。
特に中学3年生の受験対策講座になると、講習回数が増えたり模試が含まれたりするため、10万円以上になるケースも珍しくありません。
また、個別指導塾では1コマ単位での申し込みが可能な場合もあり、必要な教科だけ選べる反面、単価はやや高めになる傾向があります。
入会金や教材費、模試費用が別途必要になる場合もあるため、申し込み前に確認をしておくことが重要です。
夏期講習は何日くらいですか?
夏期講習の期間は塾によって異なりますが、おおむね2~4週間程度が一般的です。夏休みの前半・後半に分けて実施する塾もあれば、お盆を挟んで連続で開催する塾もあります。
通塾頻度や授業時間もさまざまで、週3回ほどのゆったりしたペースから毎日のように通う集中型まで選択肢は多岐にわたります。1日に2~3コマの授業を受けるパターンが主流ですが、集中的に強化したい科目がある場合は、1日に4~5コマ受講することも可能です。
家庭のスケジュールやお子さまの体力、集中力に合わせて無理のないプランを選びましょう。日程が合わない場合に補講ができるかどうかも事前に確認しておくと安心です。
中学3年生で夏期講習を受けている割合は?
地域や家庭環境によっても異なるため、あくまでも目安にはなりますが、中学3年生の約2人に1人は高校受験を意識して夏期講習を受講しているといわれています。
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000149.000030850.html
夏休みはまとまった勉強時間が確保できる貴重な期間であり、学力の底上げや志望校対策、模試に向けた実力強化など、夏期講習の活用は受験準備の一環として重視されています。
普段は塾に通っていない生徒であっても、夏期講習だけスポットで参加するケースも増えており、受験を控える中3生にとっては「勝負の夏」として位置付けられることが多いといえるでしょう。
まとめ
今回は塾の夏期講習について解説しました。夏期講習の受講はデメリットもありますが、それ以上に得られるメリットは大きいものです。
本記事で挙げた注意点を意識して上手に塾選びをしましょう。特に受験を控えているご家庭は夏期講習の受講を検討してみてください。