富田林中学校は、府立初の公立中高一貫校として開校し、今年で9回目の入試となりました。毎年倍率も高く、人気を集める富田林中ですが、2025年の入試「適性検査」の倍率や試験内容はどのようなものだったのでしょうか。
学校概要や基本的な入試方法などについては、以前の記事「大阪府立で初の中高一貫校!大注目&高倍率の大阪府立富田林中学校」に譲り、今回は2025年の最新情報を中心に「適性検査」の内容に話題を絞り込み、実際に富田林中受検を検討しているお子様の参考になる、掘り下げた情報をご紹介していきます。
まずは、2025年の富田林中の適性検査における倍率や概要について見ていきましょう。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

どうやって中学受験を乗り越えた?
富田林中に合格した生徒のメッセージをチェック!
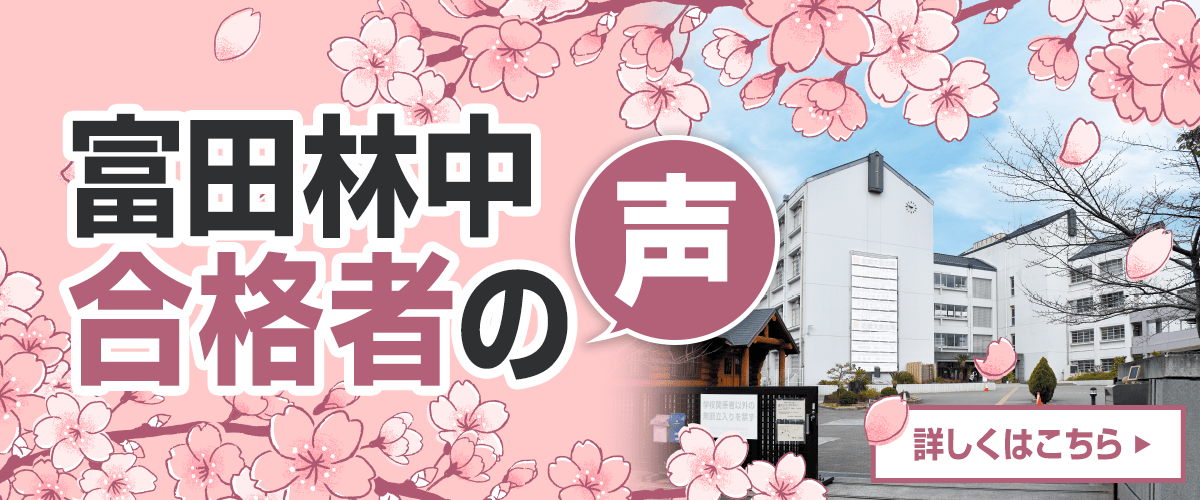
倍率は過去9年のなかで一番低い倍率
2025年の富田林中の適性検査ですが、倍率は過去9年のなかで一番低い倍率となりました。
具体的には、2025年の適性検査では、定員120名に対し、志願者数298名、「倍率2.48倍」という結果でした。
開校当初は「ダメ元でとりあえず受けてみよう」といういわゆる記念受検、お試し受検層が一定数いたこともあり、倍率が5倍を超えるなど非常に狭き門でした。
しかし、開校してある程度期間が経ったこと、少子化の影響、そして2020年からはコロナ禍で受検校を絞る傾向も強いことから倍率はさらにゆるやかになりました。さらに、大阪府では2024年度から私立高校の授業料が実質無償化されたため、公立中高一貫校への入学を慎重に考えるご家庭が増えている傾向にあります。
公立高校であれば人気がある学校でも倍率1.5倍ほどであることを考えると、富田林中は非常に人気があり、入学が難しいことには変わりありません。 今後も引き続き、「地域の人気校」でありつづけ、一定の高い倍率となることが予想されるでしょう。
また、2026年の募集人員が例年の120人から105人に減るため、倍率が高くなる可能性もあります。
参考:https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/106573/03_honbun_1.pdf
倍率の推移
| 年度 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|
| 2017年 | 603人 | 5.03倍 |
| 2018年 | 497人 | 4.14倍 |
| 2019年 | 434人 | 3.62倍 |
| 2020年 | 425人 | 3.54倍 |
| 2021年 | 374人 | 3.12倍 |
| 2022年 | 330人 | 2.75倍 |
| 2023年 | 302人 | 2.52倍 |
| 2024年 | 335人 | 2.79倍 |
| 2025年 | 298人 | 2.48倍 |
私立中学と併願する生徒も
地域でも、富田林中と同じような適性検査型の入試を実施する私立中学校が複数あるため、同様の入試形態の学校を中心に併願受検をする生徒がいます。
併願受検は、もし富田林中に不合格になった場合でも進学先として押さえておきたいのが目的ですが、一回勝負の適性検査本番に備えて試験の経験を積むことを目的としている生徒もいるようです。
適性検査(入試)の概要
2025年の富田林中の適性検査の概要は、以下となります。
適性検査の概要
| 試験内容 | 配点(時間) |
|---|
| 適性検査Ⅰ(国語的問題) | 100点(45分) |
| 適性検査Ⅰ(英語的問題) | 20点(10分) |
| 適性検査Ⅱ(算数的問題) | 100点(45分) |
| 作文(400字程度) | 60点(30分) |
| 適性検査Ⅲ(社会・理科的問題) | 100点(45分) |
参考: https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/62076/00_jissiyokou.pdf
適性検査の内容は、私立中学校の入試のように小学校の教科書内容を超える事柄は出題されません。ただ、特徴として、長い問題文を読んだうえで、様々な条件を考えて答えを出す・記述をするといった特殊な問題が出題されます。
このような「読解力」「論理的思考力」「表現力」などが必要とされる例年の問題傾向は、2025年適性検査においても継続されていました。
具体的な科目別の内容については、次項目で見ていきましょう。
富田林中適性検査の出題傾向と対策
2025年に出題された問題の最新情報を中心に、富田林中の適性検査の出題傾向と対策について解説します。
適性検査Ⅰ「国語的問題」
適性検査Ⅰ「国語的問題」では、大問が3つ。大問の大まかな内容としては、論説文が2題、資料を読み解く問題が1題となっています。
論説文的随筆では、毎年自然科学の内容が多く、2025年も「ホタル」についての随筆でした。富田林中学校・高校はスーパーサイエンスハイスクールという、理系に力の入った学校であることから、自然科学の問題が頻出されるようです。
2025年は近年の適性検査と比べると易化した傾向になりました。理由としては、記述量の減少にあり、2024年と比べると記述問題数に差はあまり無いものの記述文字数が減少し、記述力によって点数の差が生じました。
2025年度は合計135字の記述が求められ、記述慣れができていたか、きちんと対策できていたかが重要になりました。
国語の適性検査で求められる力として、「問題分析能力」「本文読解能力」「記述解答作成能力」が挙げられます。問題文のなかから何をどこに探せばよいのかを瞬時に判断し、本文の内容もしっかりと理解する必要があります。
記述に苦手意識のある生徒でも、積極的に取り組んで記述慣れすることが求められるでしょう。
適性検査Ⅰ「英語的問題」
2025年度より適性検査に「リスニング」が組み込まれました。
大問5題で構成されており、全て4択式となっています。時間は10分、得点は20点満点です。全ての問題がイラストを見ながらのスピーチや会話のリスニングになります。
リスニングの適性検査で求められる力として大きく3つあり、まず、10分間継続して音声を聞き取れる「耳慣れ」、2つ目に「話す」「聞く」「書く」の訓練を通じて全てを支える「単語への慣れ」、そして、聞くことに慣れて単語力を身につけたうえで出題傾向に基づく「問題への慣れ」が必要になります。
英語への慣れを養うために、塾などで計画的に学習を続けることが重要といえるでしょう。
適性検査Ⅱ「算数的問題」
算数的問題では、大問が4つ。
整数問題、速さは頻出単元です。整数問題では最小公倍数や最大公約数、速さで言うと追いつく問題などが複合的に出題されていました。
図形・思考力問題では、平面図形、空間図形は大問1からよく出題され、規則性もよく出ています。近年では、さいころの問題が出題される傾向にあります。平面図形、空間図形の基本的な性質を理解して、複雑な図形の面積や体積を求められるような練習が必要になります。
富田林中の算数のポイントは、範囲を絞るというよりは幅広く学習する必要があります。また、標準問題から発展問題まで複合的な問題が出されますので、色んな問題をしっかりやっておかないと対応ができなくなります。
全体的に問題文が長いため、条件を整理して表・図から素早く正確に情報を受け取る力が必要になります。記述は毎回出題されていますが、根拠となる式、答えを書ければ得点できるような問題です。長く書くと時間がかかってしまうため、端的に書けるような練習が必要となります。
富田林中の算数的問題を解くうえで必要な力としては、まず、「工夫して早く正確に求められる力」が挙げられます。基本の四則計算に加え、逆算や計算の工夫ができることが求められます。
次に、「複雑な図形の面積・体積にも対応できる力」も大切です。図形の性質を理解したうえで問題を解いたり、複合的な問題を解けたりするようになる力が必要といえるでしょう。
必要な力を身につけながらスピードを意識して問題を解くことが大切になります。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

どうやって中学受験を乗り越えた?
富田林中に合格した生徒のメッセージをチェック!
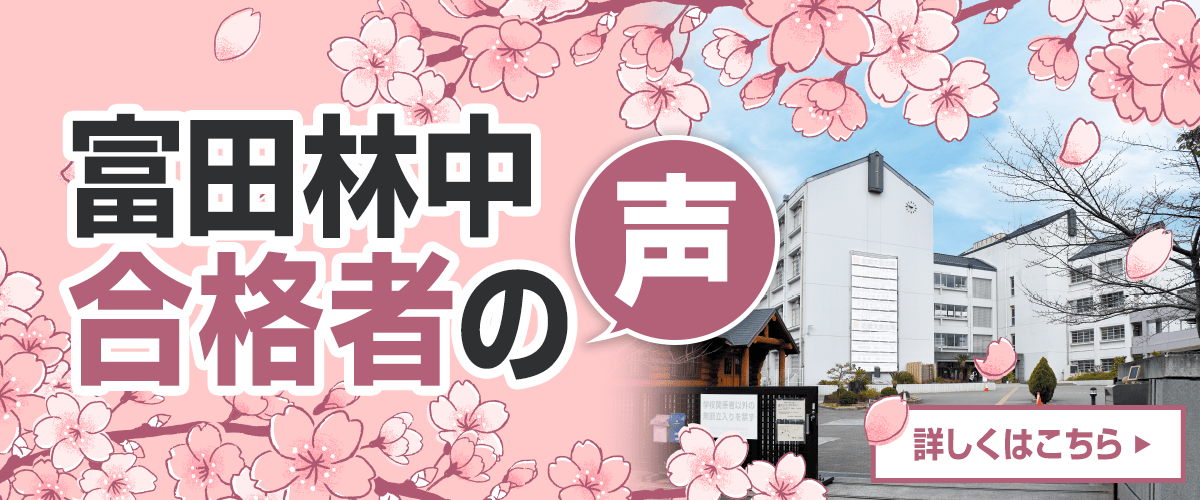
適性検査Ⅲ「社会・理科的問題」
適性検査Ⅲは、「社会・理科的問題」となります。2025年の配点は、社会が50点、理科が50点という内訳でした。
理科
2025年の理科は、「もののとけ方」「ふりこ」などの頻出単元が出題されましたが、単にとけ残りの量や周期などの数値を求める従来のものではなく、図や表など問題文からわかることをまとめるような問題となりました。また、例年あまり見られなかった算数的な問題も出題されたため今後はより総合的な学習が求められます。
小5の単元では、2024年度の出題と似ているため、次年度は「天気の変化」や「電磁石の性質」の出題の可能性が高いと予想されます。小6の単元では最終学年のため、幅広い単元の出題となっていました。
近年の特徴として、理科と社会の融合的な問題は引き続き出題されているため、理科と社会はセットで学習していく必要があります。また、3、4年生の単元からの出題が増加しているため、今までよりも更に早期からのきちんとした学習が必要になります。学年別の配点を見てみると、小3・小4・小5の単元は50点のうち14点を占めています。
理科に必要な力は、教科書レベルの基礎知識を確実に身につけることです。また、暗記だけではなく実験の手順・器具の使い方、その理由まで正しく理解しておくことも必要です。実験の意味や、なぜそうするか、それで何が分かるのかをきちんと理解しましょう。
そのうえで「長い説明文や図・表・グラフを読むことに慣れておく」ことも必要になります。最後に、出題化されている学年が広がっているため今までよりも幅広い学年、単元の学習が不可欠となります。
きちんと図表を読み取り、論理的に考えられるよう日頃から練習しておきましょう
社会
社会の問題は、地理分野6問、歴史分野4問、公民分野3問、また、思考力を問う問題1問が出題され、2024年度より地理分野が1題増加しました。
基本的には知識を問う問題でしたが、地形図や資料を読み取っての正誤判定・記述問題など差がつく問題が見られました。そして2024年度に続いて世界の主な国の地理を問う問題や都道府県を文章から答えさせる問題が出題されました。
難易度が高いテストでもなく、配点が特に高くなっている問題があったわけでもないため、1問でも多く得点することが合否を分けました。
小5の学習内容であれば地形図はほぼ毎年出題されており、対して工業や運輸貿易など、全く出題されない単元もあります。今後も絶対に出ないと言い切れず対策は必要となるため、幅広く知識を定着させていく必要があります。
小6の単元では、歴史分野は幅広く、特に明治時代以降の近現代史の出題頻度の高さは富田林中の大きな特徴のひとつと言えるでしょう。公民分野からの出題も毎年あり、小6から学ぶ内容であり学習時間が短くなるため注意が必要です。
幅広い出題となっているため、日頃からの基礎内容の反復、そして実践問題の練習度合いが非常に重要になってきます。単なる暗記にとどまらず、「なぜ」まで考えることで連結した知識・教養になっていき、臨機応変に対応できるようになります。
社会に必要な力として、まずは基本的な語句がすぐに答えられるように徹底した知識のインプットが必要になります。ただし、単なる暗記にならないよう、その語句自体や前後の関係を説明できるよう「背景」と「理由」、「影響」までをセットで理解することが大切です。
そして、情報をすばやく正確に読み取り、考えたことを論理的に記述する力も求められます。普段から「なぜ」「どのようにして」「どうすればいい」といったことを考える習慣を身につけて思考力を養いましょう。
作文
作文では、与えられたテーマに沿って自らの体験と考えを書きます。2025年のテーマは「旅」で、文字数は361字~440字以内であり、例年は段落数や段落ごとの内容など構成も指定されていましたが、2025年の作文では指定がありませんでした。
「筆者の考え方を理解し、それに対して自らの考えを具体的に表現」しつつ、読者=採点者にとって「より分かりやすい具体的な体験」を必ず書くことが求められます。求められるもの、必要なものを瞬時に判断して書けたかどうかが得点の分かれ目となりました。
「抽象的事実」と「意見・感想」のバランスを考慮し、適切な文章構成を考えた上で作文を書ききることが高得点のチャンスになるでしょう。
問題文をしっかり読み、求められているものを求められている通りに書くことが重要となります。そして読み手に分かりやすく伝えるための表現力が求められます。
富田林高校の大学合格実績は?

2017年に中高一貫校に移行した富田林中学校と富田林高等学校ですが、2023年度は中高一貫校として入学した生徒たちが初めての大学受験する年となり、3年目となる2025年は中高一貫教育の成果が表れ始め合格実績が着実に伸びを見せた大学受験でした。
中高一貫校になったことで大学合格実績はどのように変化したのでしょうか。
近畿地方の難関大学を中心に過去7年間の合格実績の推移を見てみましょう。
| 大学分類 |
大学名称 |
2025年(現役)
富田林中3期生
|
2024年(現役)
富田林中2期生 |
2023年(現役)
富田林中1期生 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
| 国公立大学 |
京都大学 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| 大阪大学 |
16 |
8 |
11 |
1 |
1 |
1 |
3 |
| 神戸大学 |
3 |
4 |
6 |
1 |
4 |
0 |
1 |
| 大阪公立大学 |
31 |
15 |
21 |
23 |
20 |
12 |
15 |
| 私立大学 |
関西大学 |
113 |
112 |
114 |
111 |
131 |
125 |
118 |
| 関西学院大学 |
56 |
35 |
35 |
43 |
33 |
34 |
29 |
| 同志社大学 |
32 |
33 |
48 |
19 |
21 |
13 |
24 |
| 立命館大学 |
32 |
18 |
22 |
17 |
13 |
15 |
21 |
※分かりやすくするため、2023年以降の実績は浪人を除く現役合格者数で表示
※大阪公立大学は2019年~2021年については大阪市立大学、大阪府立大学の合算
今回挙げた大学のうち、2024年度と比較すると大幅に合格者数が増加した大学が多数ありました。
また、中高一貫校となる前の年度と比べると難関大学への進学実績は増加しているため、中学受検で入学した学生の学力が平均的に高いと言えるでしょう。
それに伴って授業の難易度も高くなりますが、学力のばらつきが少ないので授業もスピーディーに進み、優秀な学生が育ちやすい環境となったといえます。
今後、早期の進路指導、大学受験対策のノウハウが蓄積されることで、更なる合格者の増加に期待できます。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

どうやって中学受験を乗り越えた?
富田林中に合格した生徒のメッセージをチェック!
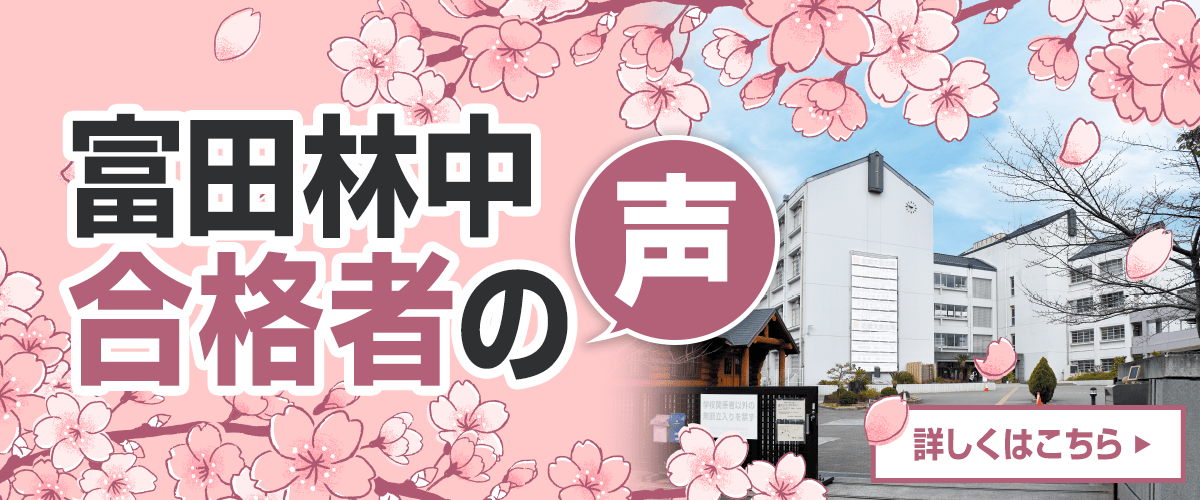
8年連続、合格者の半数近くが第一ゼミ生
塾別の合格者数は、第一ゼミナールが富田林中開校以来8年連続No.1となっています。ですが、最初から成績がいい、合格しそうな生徒だけを選抜して指導しているからこの実績というわけではありません。
日々、生徒一人ひとりに寄り添い、一緒に課題を克服していく「生徒第一・1/1(いちぶんのいち)の教育」の丁寧な継続が成績向上、そして志望校合格につながっていると考えています。