「子どもが中学受験をする予定だけど、いつから準備すればいいのか」
そうお悩みの親御さんも多いのではないでしょうか。
中学受験を考えている場合、小学校4年生(厳密には小学3年生の2月)から塾に通い始める子どもが多いと言われていますが、最近では低学年から塾に通い始めるケースも増えています。
今回は、子どもの中学受験はいつから準備すればよいのか、塾に通い始める学年別のメリットやデメリットを解説していきます。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

この記事は、顧客満足度No.1の関西で展開する学習塾
「第一ゼミナール」が監修しています。
この記事は、顧客満足度No.1の
関西で展開する学習塾
「第一ゼミナール」が監修しています。
中学受験で塾に通うタイミング
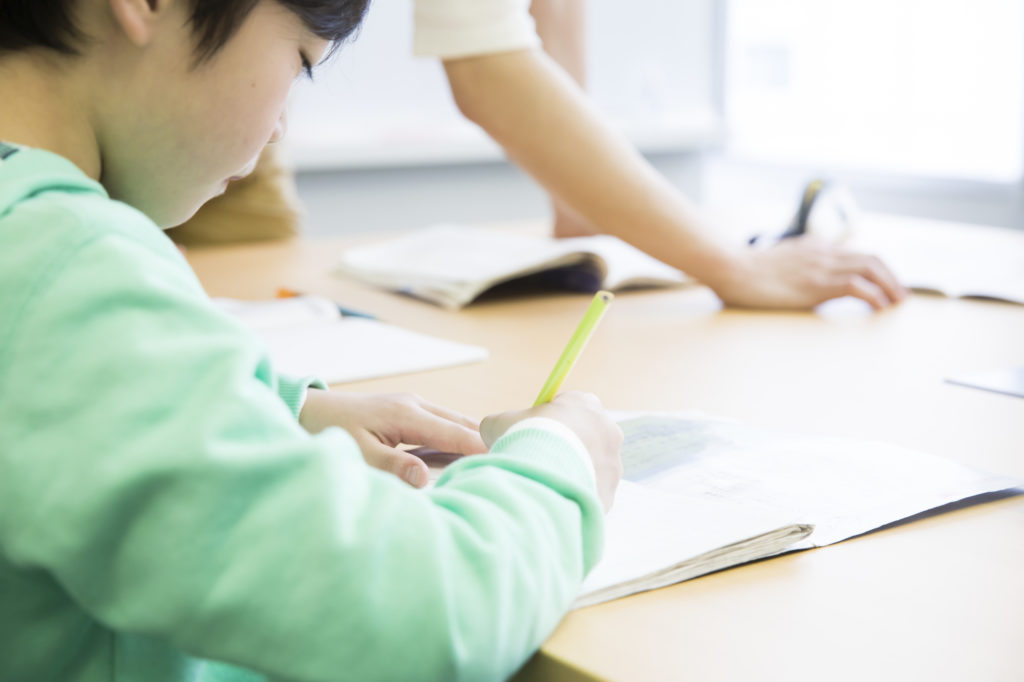
中学受験をする子どもの中には、家庭学習だけで受験を乗り越える子どもも少数いますが、試験で出題されるのは小学校で習う内容よりも難しく高度な問題になるため、塾に通って対策をすることが一般的です。
では、実際にいつから塾に通い始める子どもが多いのでしょうか。
小学4年生から塾に通う子が多い
冒頭の通り、中学受験の準備として塾に通い始めるのは、小学3年生の2月から始まる「新小学4年生」からが一般的だとされています。
中学受験の塾は、新年度が「2月」から開始されます。なぜ「2月」から開始されるのかと言うと、中学受験の入試は関東では毎年2月の上旬、関西では毎年1月の中旬に集中して行われており、中学受験の塾の新年度も中学受験の試験本番の時期に照準を合わせて、カリキュラムを組んでいくからです。
そして、小学4年生からの通塾が多いのは、中学受験の準備にはおよそ「3年」は必要だと言われているからです。
この中学受験の3年間は、まず小学4年生で塾に通うことに慣れ学習する習慣を作り、小学5年生では中学受験に必要な大量の知識や技術を本格的に学んでいきます。そして、小学6年生では過去問を解いて応用問題に取り組んでいき、確実に力をつけていく、という大まかな流れがあります。
このような考えのもと、塾では小学4年生から中学受験のコースが開講されることが一般的で、実際に中学受験を考える多くの子どもは小学4年生から通い始めています。
低学年から中学準備をする子どもも
近年、中学受験を志向する子どもが増加傾向にあり、小学4年生から開講されるコースがすぐ定員に達して入塾できないケースが出てきています。そういった背景から、席の確保を目的に小学1~3年生といった低学年のときから塾に通うケースがあります。
実際に中学受験を検討されている親御さんは、検討している近隣の塾の空き状況を問い合わせて確認するといいでしょう。
また、「中学受験の準備」は、中学受験の塾に通い始めることだけではありません。塾に通わなくても親御さんがサポートできることがあって、勉強する習慣を小学1~3年生のうちから身に付けておいたり、将来の夢や仕事の話題に触れて視野を広げてあげることも立派な「中学受験の準備」と言えます。
低学年のうちに家庭でできる「中学受験の準備」は後ほど詳しく紹介いたします。
学年別でみる中学受験の準備

小学4年生から中学受験の塾に通い始める子どもが多いと述べましたが、それよりも早い低学年だったり、小学5・6年生など遅いタイミングで入塾される家庭もあります。
自分の子どもをいつから通い始めさせるべきか。
以下、学年別に中学受験で塾に通い始めるメリットとデメリットを解説します。
小学4年生|一般的な中学受験のスタート時期
まずは、中学受験で一般的だとされている小学4年生から見ていきましょう。
メリットは「学習習慣の確立」「基礎力の定着」
小学4年生から中学受験の塾に通い始めるメリットは、主に「学習習慣の確立」と「基礎力の定着」です。
そもそも、中学受験の勉強がより本格化するのは、小学5年生からだと言われています。小学5年生はそれまでと比べ学習内容も一段と難しくなり、塾に通う回数も増えていきます。
「では通塾は小学5年生からでも良いのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、本格的に受験勉強が始まる小学5年生から塾に通い始めても、毎日机に向かい勉強をする「学習習慣」が確立されていなければ、子どもはとても苦労します。
そこで、小学5年生になる前の小学4年生から塾に通うことで、今後膨大な知識や技術を学ぶために必要になる土台の部分、つまり「学習習慣」を定着させることができるのです。
小学4年生までは通塾回数が週2程度の塾が多いのですが、まずは塾に行くことに慣れること、そして、学校の勉強以外にも中学受験に向けた勉強をする習慣をつけることが大切なのです。
また、学習内容の難易度が小学5年生からぐんと上がる前の時期だからこそ、小学4年生のうちに「基礎力」をしっかり定着させておくことも大切です。
この時期に分からないことをなくして苦手分野を潰しておくことで、中学受験を有利に進めていくことができるのです。
頑張りすぎて、小学5年生で中だるみする子も
デメリットは、最初はやる気で溢れていたものの、頑張りすぎた結果、中学受験の勉強がより本格化する小学5年生でスランプに陥ってしまうことです。
小学4年生の時期から全力で頑張ることはとても大切なことですが、あくまで「土台作り」の時期であることを理解しておかないといけません。
最初からアクセル全開で頑張りすぎて小学5年生で失速することのないように、子どもが力みすぎていたらリラックスさせてあげることも時として必要です。受験勉強を3年間続けるモチベーションを保ち続けられるように、志望校の文化祭などのイベントに連れていってあげるなど、何か子どもの息抜きをしてあげることも必要です。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

小学5~6年生|中学受験の勉強が本格化する時期

先述した通り、小学5年生から中学受験の勉強は本格化し、小学6年生からは応用問題や過去問題に取り組むようになります。では、小学5、6年生から塾に通い始めても間に合うのでしょうか。
遊び時間を作って短期集中で仕上げる
小学5年生からは塾で習う勉強の難易度が上がり覚える知識が増えていきます。また塾に通う回数も週2から週3回以上になって、同時に予習・復習、宿題など日々のタスクも増えてきます。
それまでに「学習習慣がついている子ども」、かつ、「中学受験に必要な基礎力が定着している子ども」であれば、勉強期間が短い小学5年生以降の入塾でも問題がないケースもあります。
小学5年生から中学受験の勉強を始めたのであれば、勉強期間は2年間で済ませることができます。小学生というまだまだ遊びたい時期なので、できるだけ遊びや習い事に時間を割いてあげたいと考える親御さんもいらっしゃることでしょう。
子どもの時間を大切にしつつ、中学受験の勉強を短期集中で仕上げたいと考えている方にとっては、小学5、6年生からの通塾開始のメリットは大きいです。
遅れを埋められず失敗してしまうことも
短い勉強期間で結果を出せれば良いですが、小学5年生から入塾したあとに苦手な分野が判明してつまづいてしまうと遅れをとってしまうこともあります。
他の多くの生徒が小学4年生から開講されるコースで学んできて、塾のカリキュラムに則って基礎力を着実につけているのに対して、自分だけスタートラインが違うと不安になってしまう子どももいるかもしれません。
早くから中学受験をスタートしている周りとの学力のギャップをカバーできるのかは、子どもの頑張り次第でしょう。
大切なのは、小学6年生の年明けにある中学受験の本番の時期に、学力と精神力をピークに持っていくことです。子どもの日ごろの学習の取り組みや成績、そして性格を考慮して、小学5、6年生からの通塾で問題ないか考える必要があります。
小学1~3年生|周囲より早い時期
この数年、教育熱の高まりや中学受験者数の増加で、小学1年生からのコースを開講している中学受験の塾が増えてきました。
「周囲が小学4年生から始めるなら、さらに早いスタートダッシュは有利になるのでは?」と考える親御さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
低学年から楽しく学んで基礎力をつけられる
低学年から塾に通い始めるメリットとしては、学習習慣をしっかりつけられること。そして、中学受験に必要な基礎力を低学年のうちから楽しみながら無理なく定着させられることです。
「低学年のうちから中学受験の塾なんて早い」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、低学年のコースでは「中学受験のための勉強」ではなく「勉強に興味を持つために好奇心を刺激するカリキュラム」を意識している塾もあります。
子どもが「勉強をしている」という気持ちではなく、クイズ感覚や遊びの感覚で楽しく思考力を養い、数や科学に親しむことができるコースもあるのです。
低学年であれば通塾回数も週1回程度の塾も多く、負担は軽いと言えます。学ぶことが好きで学校の授業だけでは飽き足らない子どもや、探求心の強いタイプの子どもは、低学年からの塾通いに向いていると言えるでしょう。
また先ほど説明したように、塾によっては中学受験のコースが開講される小学4年生ではすぐに定員に達している塾もありますので、「席の確保」という意味でも、周囲より少し早めに塾に通い始める意味はあるかもしれません。
早期のスタートダッシュで息切れしてしまう子どもも
周りの子どもより先に塾に通って基礎力や勉強の土台作りをしておけば、中学受験でよいスタートダッシュを切れることもあるでしょう。
ただ、低学年の頃から遊びを減らし、勉強時間を増やして順位が出るテストを受けるなど競争する環境にいることで、息切れしてしまう子どもがいることも事実です。
勉強に対する苦手意識や嫌悪感を持ってしまうことは、中学受験をするうえでどうしても避けておきたいことです。
ただ、子どもによっては学校とは違う高いレベルで勉強ができ、知的好奇心を刺激する塾が楽しいと感じることもあります。低学年から塾に通い始めるべきか、子どもの性格、塾のカリキュラムや通塾のスケジュールを踏まえたうえで検討しましょう。
家庭でできる「中学受験準備」

最後に、塾に通い始める前に家庭でできる中学受験の準備についてご紹介します。
今すぐに取り組めるものばかりですので、是非参考にしてください。
読書する
読書は、語彙はもちろん幅広い知識や論理的思考力を培うことができます。読書をする習慣がない子どもには、親も一緒に読み聞かせをして本に触れる時間を取ると効果的です。
また、音読をすることで読解力の向上や速読にもつながり、記憶力にもいい影響があると言われています。家で読書の時間をしっかりと取ることで、先で待っている中学受験に役立つことでしょう。
図形の苦手意識をなくす
中学受験で苦戦するのが算数の図形問題です。
平面図形や立体図形、回転体などを自分の頭で想像できなくて、問題を解くのに苦労する子どもは多いです。
小学5年生から本格的に勉強を始めてからたくさんの過去問や応用問題を解いていきますが、低学年の頃からブロックや積み木、パズルゲームなど遊びながら図形に親しんでおくことで、苦手意識がなくなり図形をイメージする力が養われます。
科学や歴史に興味を持たせる
中学受験では国語や算数だけではなく、理科や社会も受験科目として必要となってくる学校がほとんどです。
少しでも子どもに興味を持ってもらうために、自宅で簡単な理科実験を体験させてあげたり、歴史漫画を読んで楽しみながら知識を身に付けるなど、子どもの好奇心を刺激してあげましょう。
教科書やノートを開く以外にも学べることはたくさんありますので、親も一緒に考えてあげることが大切です。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

まとめ
以上、中学受験の準備のタイミングについて解説しました。
中学受験で塾に通うのは一般的には小学4年生からですが、子どもの性格や現状の成績、勉強に対する意識によっては前後することも検討してよいでしょう。
家庭でできることもありますが、塾に通うことで学習習慣を身に付けたり基礎力向上など中学受験の土台作りができます。
志望中学校の合格に近づけるように、お子さんにとって適切な時期に入塾して中学受験の準備をしていきましょう。