小学生の宿題の定番である音読。
「音読って意味あるの?」「黙読できていれば十分なのでは?」と疑問に思う保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、小学生に音読の宿題が課されるのには大きな理由があるのです。また、音読の効果をさらに高めるために親ができる工夫もあります。
本記事では、小学生が音読する効果や、子どもが音読をしているときに親が気を付けたいことを解説します。
小学生、中学生、新入会生受付中!
今なら【冬期講習無料特典】あり

音読ってそもそも何?

音読の効果について話す前に、音読とはどのような読み方を指すのか整理してみましょう。
朗読、黙読との違い
音読と、よく似た言葉である朗読、黙読の意味は以下の通りです。
- 音読:声に出して文章を読むこと
- 朗読:読み手を意識しながら、感情を込めて声に出して読むこと
- 黙読:声を出さずに文章を読むこと
ここで確認しておきたいのが、特に音読と朗読の違いです。音読は「自分の理解のために」読み、朗読は「読み手の理解のために」読むことを言います。
朗読するためには音読できることが必須であるため、朗読の方が難易度としては高くなります。小学生の低学年と中学年は音読、高学年になると朗読ができることを一つの目安とするとよいでしょう。
音読は内容を理解することも大事
音読の宿題は小学生の低学年から始まり、長ければ小学6年生まで宿題として課される学校もあります。
このように長い付き合いになる音読ですが、音読時に注意したいのが「内容を理解しながら読むこと」です。宿題をこなすために、慣れてくるとただ声を出す事務的な作業になりがちです。
大切なのは、声に出すことと並行して内容を考えて理解すること。子どもの音読の宿題に付き添う際は、内容がきちんと頭に入っているのか見てあげましょう。
小学生が音読をする効果

では、具体的に小学生が音読をする効果としてはどのようなものがあるのでしょうか。
語彙力・読解力が向上する
まず、小学生が音読をすると語彙力が増える効果があります。
まだまだ知らない単語が多くある小学生ですが、できるだけ多くの文章に触れることで語彙力を高めることができます。黙読をするときも初めての単語に出会うことはありますが、黙読だとどうしても分からない単語は飛ばして読みがちです。
一方で、音読だとその単語を声に出して読まないと先に進めないことから、読み方や意味について考えたり調べたりするきっかけになります。そして、語彙力が蓄積されると読解力も向上します。音読することで文章の流れ、文節などの構造も意識できるようになり、文章の読み方も学べます。
黙読のスピードが速くなる
語彙力、読解力が高まり、文章をまとまりとして捉えられるようになると、黙読のスピードも速くなります。
黙読のスピードが速くなると、読書をする楽しさがより感じられるようになり、さらに多くの文章を読みたくなります。そうなると、さらに語彙力・読解力も上がる…というように良い循環が生まれます。入試の際に、問題文を早く読めて、テスト時間の間で解く時間を確保することもできます。
脳が活性化する
音読をすると、脳が活性化するという効果もあります。音読は、脳の「前頭前野」を使います。前頭前野は、記憶、判断、思考、創造、集中など人間の行動のキーとなる働きを司っています。
音読するときに、文章を見る、声に出して読む、読んだ声を聞くなど、複数の動作を同時に行うことで、前頭前野をさらに活性化させます。この前頭前野はワーキングメモリーに関わる部位であるため、勉強を始める前に音読を行うと勉強自体の効果が向上すると言われています。
集中力が高まる
音読の効果として、集中力が養われることも挙げられます。先述の通り、音読することで「集中する」行動を司る前頭前野を活性化させます。
また、音読は、声に出して読むために間違いを認識しやすいという特徴も。そのため、「間違えないように読もう」という意識が自然と働き、集中力を高められます。
人との話し方を学べる
音読で正しい日本語を大きな声で出すことにより、話し方を学ぶことができます。これは声に出して文章を読むことで、自然と読み手を意識するようになるからです。
声の大きさ、滑舌、スピード、語彙、時には感情表現の仕方など、音読を通して人とのコミュニケ―ションの仕方まで学ぶことができるのです。
小学生、中学生、新入会生受付中!
今なら【冬期講習無料特典】あり

音読の効果をさらに高めるために親ができること
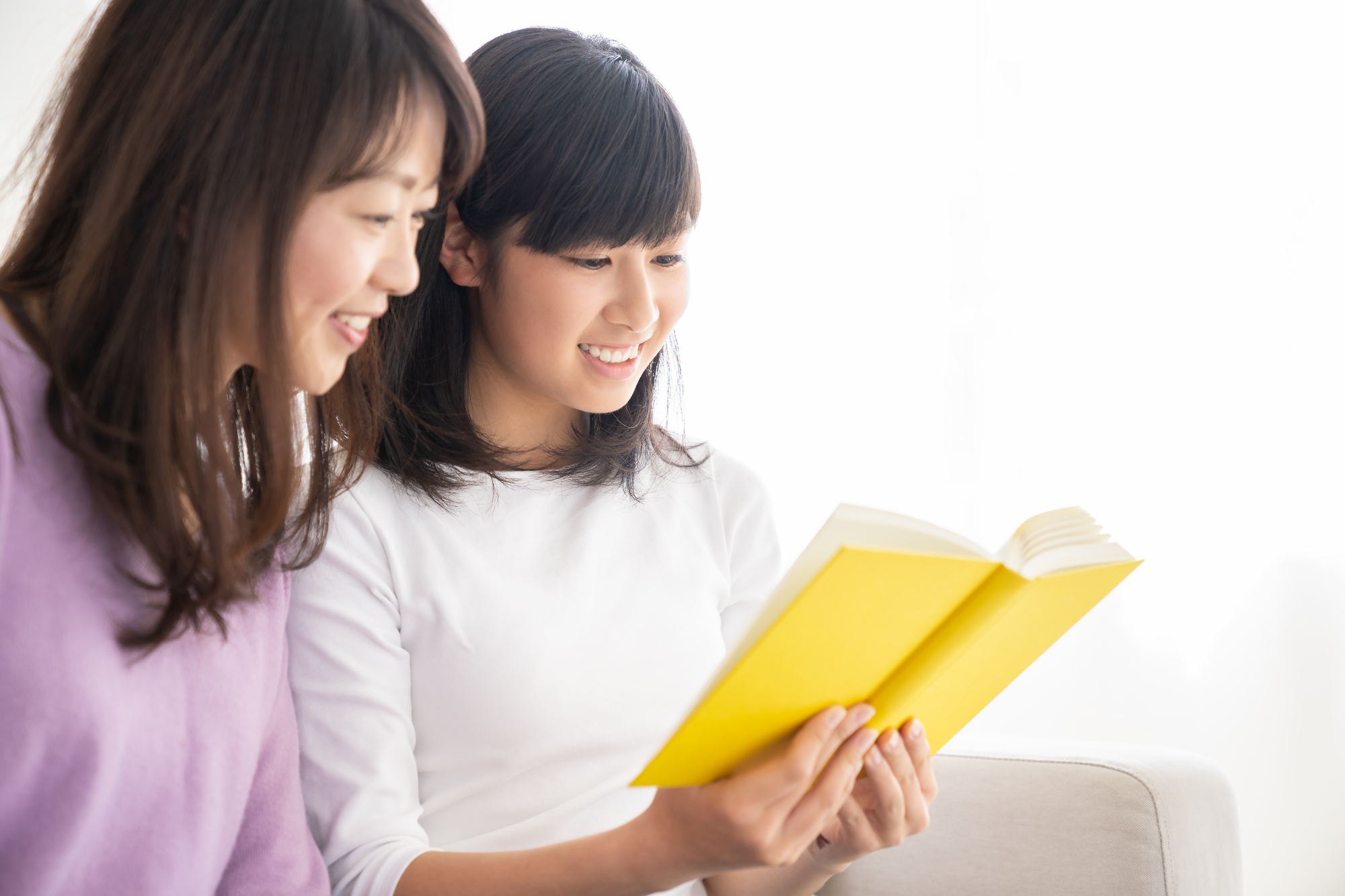
音読にはさまざまな効果があることが分かりました。しかし、親の関わり方次第では、音読の効果をさらに高めることもできますが、逆に低くしてしまうこともあるので注意が必要です。
続いては、音読の効果を高めるために親ができる工夫について解説します。
親は手を止めて音読を聞く
小学生が音読の宿題をしているとき、親も忙しく家事をしながら聞いてしまうことも多いのではないでしょうか。しかし、音読の効果をさらに高めるには、一度手を止めて「私はあなたの音読を聞いているよ」という姿勢を見せることが大切です。
親が「ながら聞き」ではなく、正面から自分の音読を聞いてくれることで、子どもの集中力もさらに高まり音読の効果もアップします。
すらすら読めなくても怒らない
子どもが音読をしているときに間違えると「違うよ、〇〇だよ」「つっかえないで読んで」などつい指摘してしまう方もいらっしゃるかと思います。子どもは読み手を意識することで集中力が高まりますが、失敗を恐れすぎると萎縮してしまいます。
子どもがつまっていたら最低限のフォローはしながらも、基本的には怒らず温かく見守ることでさらに子どもは音読をのびのびと楽しむことができ、効果も高められます。
音読した内容について質問をする
音読の効果をさらに高めるには、音読が終わったあとすぐにその内容について質問するといいでしょう。
「〇〇(登場人物)はそのときどんな気持ちだったのかな?」など、物語の内容に関することはもちろん、その他にも「あの〇〇のセリフで声を小さくしたのはなぜ?」など、子どもの音読方法について具体的に質問をするのもよいでしょう。
音読した内容について質問することで、子どもが文章を理解しているかどうかも把握でき、一緒に内容を考えることで読解力も高まります。そして抑揚などの朗読方法についても質問をすることで、音読スキルもアップします。
小学生、中学生、新入会生受付中!
今なら【冬期講習無料特典】あり

まとめ
以上、小学生が音読する効果について解説しました。
小学生に音読の宿題が課されるのは、音読にそれだけ多くの効果があるからです。そして、音読の効果を親の工夫次第でさらに高めることもできます。
「たかが音読」と思わないで、親も手を止めて音読を聞き、質問をしてあげるだけで、音読により国語力の基礎を培うことができます。ぜひ、子どもの音読時間をさらに有意義なものにしてください。