大阪府にお住まいの中学生がいるご家庭では、公立高校の入試を検討するケースが多く見受けられます。
しかし、大阪府公立高校の入試問題は他府県と比べて少し特殊なので、きちんと内容を理解していない方も多いのではないでしょうか。
大阪府立高校の入試問題は、国語・数学・英語の3教科に関してはA・B・Cの3つの問題に分けられます。志望高校の入試問題がA・B・Cのどの問題形式が出るかを把握して、対策することが重要といえるでしょう。
本記事では、A・B・Cそれぞれの問題の特徴など、大阪府立高校の入試について解説します。難問といわれるC問題を出題している大阪府立高校の一覧や、入試に関するよくある質問も載せていますので、ぜひ参考にしてください。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

大阪府立高校の国・数・英の入試問題はABCの3つ
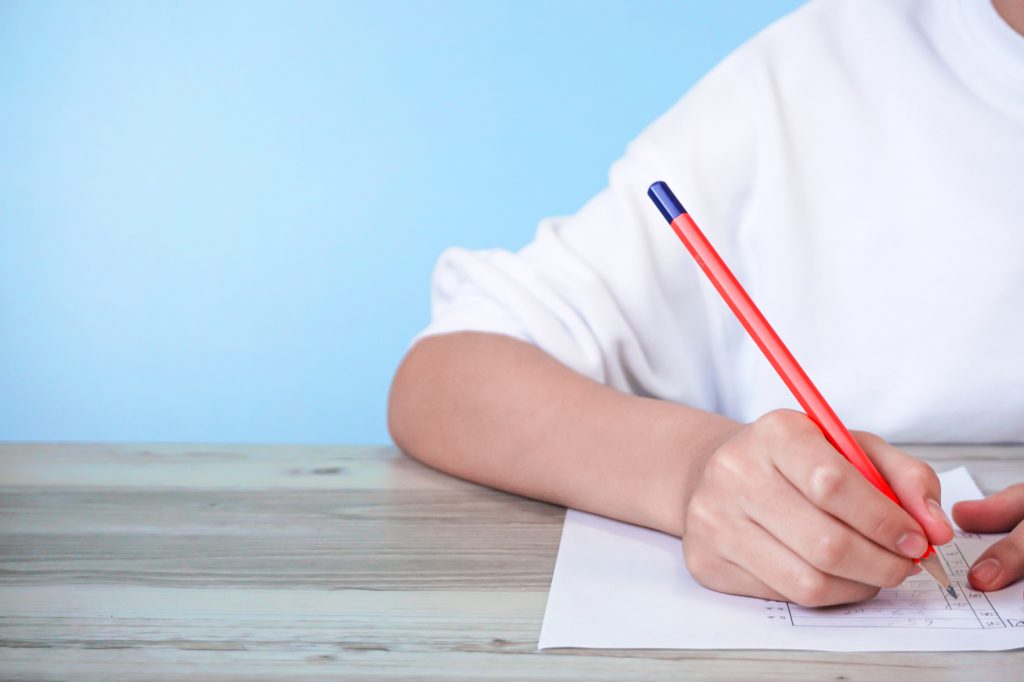
大阪府立高校の入試問題は、国語・数学・英語・理科・社会の5教科で構成されています。その中でも、国語・数学・英語の3教科は、難易度別にA・B・C問題の3パターンに分けられているのが特徴といえるでしょう。
また、A・B・Cどの問題を出題するかは、各高校が教科ごとに選択しています。
それではまず最初に、A・B・C問題のそれぞれの特徴を紹介していきます。
A問題(基礎的問題)
A問題は他と比較し難易度が易しく、基礎的問題で構成されています。
以下のような問題が出題される傾向にあります。
- 数学:教科書の基本問題で出題される公式や計算方法を理解しているか。
- 国語:基礎的な文章の理解が可能かどうか。
- 英語:教科書の例題で習う基礎的な語彙・文法・英文を理解できるか。
基本的な問題が出題されるため、ケアレスミスが合否の明暗を分けるといってもいいでしょう。A問題を出題する高校を志望する受験生は、徹底的に基礎を定着させることをおすすめします。
B問題(標準的問題)
B問題は標準的な問題で構成されており、多くの大阪府立高校で出題される問題形式です。
A問題に比べて難易度が高くなり、基礎問題だけではなく応用問題も加わります。
- 数学:公式や計算方法を知っているだけでなく、関数や図形問題の応用問題が出題されるため、過去の出題方式を参考に対策することが大切。
- 国語:A問題と比較し文章の内容が難しく、内容を理解した上で自分の意見を求められる作文問題のテーマが複雑。
- 英語:A問題では400字程度の英単語数に対し、B問題は500~600字前後の単語数と多くなり、読むスピードや正確に長文内容を読み解く理解力が重要
B問題を出題する高校のうち、偏差値が55以上の学校を志望する受験生は応用問題も解けるように対策しておきましょう。
C問題(発展的問題)
C問題は3つの中で最も難しい問題で構成されており、文理学科などの進学校と呼ばれる学校で多数選択されています。
2024年度において、1教科でもC問題を出題した大阪府立高校は26校が該当しました。
- 数学:教科書レベルではなく、応用問題が多く出題。数学が得意な人でないと最後まで解ききることが難しく、自分の得意ジャンルや比較的簡単な問題をミスなく解けるかが重要。
- 国語:評論文が出題されることが多く、中学生が普段使用しない語句が用いられているため、知らない単語でも予測しながら読む能力が問われる。
- 英語:他の問題形式と異なり、問題文も含めてすべて英語で出題。長文問題が多く出題されるため読み解くスピードが重要。英作文問題は制限字数がなく、自由度が高いため対策が難しい。
C問題は学校の授業だけで対策することは難しく、別途過去問や応用問題集などを取り入れるか、塾に通って集中的に勉強する必要があるでしょう。
大阪府立高校の入試制度について

大阪府立高校を志望する際は、大阪府の入試制度を把握する必要があります。
以前は前期・後期日程で試験日程が分けられていましたが、現在は特別入学者選抜と一般入学者選抜で分類されます。
大阪府立高校の入試制度について詳しく解説します。
特別入学者選抜と一般入学者選抜の違い
大阪府立高校の入試は、特別入学者選抜と一般入学者選抜の2種類に分けられます。
特別入学者選抜は、学力検査以外の試験を課している学科で実施される選抜方法です。体育科や音楽科、美術科などの学科が該当し、実技試験を実施することが大半となります。
一般入学者選抜は普通科や文理学科をはじめとした、公立高校を受験する多くの方が該当する選抜方式です。学力検査と調査書の評定で主に選抜されます。
特別入学者選抜で高校に合格すると、一般入学者選抜を受験することができなくなるため注意しましょう。
入試日程
大阪府立高校の2025年における入試日程は下記の通りです。
| 特別入学者選抜 | 一般入学者選抜 |
|---|
| 出願日 | 2月14日~17日 | 3月5日~7日 |
| 試験日 | 2月20日(学力検査)・21日(実技検査) | 3月12日 |
| 合格発表日 | 3月3日 | 3月21日 |
例外として音楽科は、2月4日〜5日が出願日となり、専攻の実技と視唱試験を2月15日、学力検査と聴音試験を2月20日の実施となります。
「英語」科目における英語資格の活用
大阪府立高校の入試科目の「英語」は、外部機関の英語資格のスコアを活用することが可能です。
この制度を利用する際は、外部機関の英語スコアを読み替え率に定めて点数を算出します。読み替え率から算出した点数と学力検査の点数を比較し、点数の高い方が英語科目の得点となります。
実際の読み替え率の表は下記の通りです。
| 読み替え率 | TOEFL iBT | IELTS | 英検 |
|---|
| 100% | 60点 | 6 | 準1級 ・1級 |
| 90% | 50点 | 5.5 | – |
| 80% | 40点 | 5 | 2級 |
大阪府立高校の文理学科などの難関校を受験する際、外部機関の英検やTOEFLなどの試験を取得しておくことで、難問であるC問題の対策をしなくてもいいという非常に大きなメリットがあります。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

大阪府立高校入試の合否判定

大阪府立高校の合否は、学力検査だけで合否は決まりません。中学1〜3年の9教科の成績により点数化される内申点も重要になってきます。
また、合格と不合格のボーダーラインに位置する受験生は、自己申告書の内容により合否が分かれることもあります。
この章では、実際に内申点の計算方法やボーダーラインに位置する受験生の合否判定方法について解説します。
内申点の計算方法
内申点で計算されるのは、9教科の成績を5段階評価にしたものです。1学年における満点は45点となりますが、内申書に記載する内申点は450点満点で計算します。
点数の内訳は、1年:2年:3年=90点:90点:270点です。中学1・2年生の成績は2倍され、3年生の成績は6倍したものが内申点となります。
1年生からの成績が内申書に反映されるため、得点の比率は少ないですが定期テストの点数や授業態度には1年時より注意しておきましょう。
内申点と学力検査による合否判定方法
大阪府立高校入試の合否は、内申点450点と学力検査450点の900点満点で判定されます。ただし、受験する高校によって内申点と学力検査の点数比率が異なります。
点数比率はⅠ〜Ⅴの5段階あり、内申点を重視する学校と学力検査を重視する学校によってタイプは分かれます。
下の表は比率タイプごとの内訳です。
| タイプ | 学力検査の成績にかける倍率(点数) | 学力検査の評定にかける倍率(点数) | 総合数 | 学力検査の成績:調査書の評定 |
| Ⅰ | 1.4倍(630点) | 0.6倍(270点) | 900点 | 7:3 |
| Ⅱ | 1.2倍(540点) | 0.8倍(360点) | 6:4 |
| Ⅲ | 1.0倍(450点) | 1.0倍(450点) | 5:5 |
| Ⅳ | 0.8倍(360点) | 1.2倍(540点) | 4:6 |
| Ⅴ | 0.6倍(270点) | 1.4倍(630点) | 3:7 |
文理学科のような偏差値の高い高校は、学力検査の点数比率が高いⅤタイプを選択する傾向になります。
アドミッションポリシーによる合否判定
アドミッションポリシーとは、各高校が定めている「求める生徒像」のことです。
大阪府立高校の受験では、内申点と学力検査の合計点上位110%を選出し、90%までを合格とします。残りの20%はボーダーゾーンの対象となり、内申書の活動/行動の記録欄や、受験時に提出する自己申告書の内容を参考にし、アドミッションポリシーに合っている学生を合格とします。
自分よりレベルの高い高校に挑戦してボーダーゾーンに入る可能性がある人は、手を抜かずにしっかりと自己申告書を書き上げましょう。
【2024年度版】C問題が出題された大阪府立高校の一覧
大阪府立高校のうち、C問題が出題される高校を一覧にしてご紹介します。
偏差値の高い進学校を目指している方は、どの問題形式が出題されるか確認しておきましょう。
| 学校名 | 学科名 | 数学 | 国語 | 英語 |
|---|
| 北野 | 文理学科 | C | C | C |
| 茨木 | 文理学科 | C | C | C |
| 豊中 | 文理学科 | C | C | C |
| 春日丘 | 普通科 | C | C | C |
| 池田 | 普通科 | B | C | C |
| 三島 | 普通科 | C | C | B |
| 千里 | 総合科学科
国際文化科 | C | C | C |
| 桜和 | 教育文理学科 | B | C | B |
| 大手前 | 文理学科 | C | C | C |
| 四條畷 | 文理学科 | C | C | C |
| 天王寺 | 文理学科 | C | C | C |
| 高津 | 文理学科 | C | C | C |
| 生野 | 文理学科 | C | C | C |
| 富田林 | 普通科 | C | C | C |
| 八尾 | 普通科 | C | C | C |
| 清水谷 | 普通科 | B | C | B |
| 夕陽丘 | 普通科 | B | C | B |
| 住吉 | 総合科学科
国際文化科 | B | C | C |
| 今宮 | 総合学科 | B | C | B |
| 三国丘 | 文理学科 | C | C | C |
| 岸和田 | 文理学科 | C | C | C |
| 泉陽 | 普通科 | C | C | C |
| 和泉 | グローバル科
普通科 | C | C | C |
| 佐野 | 国際文化科
普通科 | B | C | B |
| 鳳 | 単位制普通科 | C | C | C |
大阪府立高校の入試問題に関するよくある質問

最後に、大阪府立高校の入試問題に関するよくある質問を紹介いたします。
大阪府立高校の入試問題で、ABC問題の出題形式となったのはいつからですか?
大阪府立高校の入試問題が、ABC問題の3形態となったのは2016年度からです。
2016年度から大阪府立高校の入試制度が大きく変わり、自己申告書の提出や調査書の評定を相対評価から絶対評価へ変更、3月入試への一本化などが施されました。
以前の文理学科は前期入試、普通科は後期入試と分かれていましたが、現在は実技試験を必要とする学部以外は一般入学者選抜と一括りになっています。同じ学校であれば、「国際文化科」と「普通科」など複数の学科を志望できるようになったのも、大きな変更点の一つといえるでしょう。
大阪府の公立高校入試において、C問題の合格者の平均点は何点ですか?
大阪府の公立高校入試の令和5年度の合格者の平均点は、100点満点に換算した点数だと国語Cは64.3点、数学Cは51.2点、英語Cは67.3点でした。
参考: 令和5年度大阪府公立高等学校入学者選抜学力検査
平均点は毎年変動しますが、どの教科も50〜60点台となります。進学校を志望している受験生は60〜70点台を取れるように対策することで、合格へ近づくことができるでしょう。
大阪府立高校の入試問題対策として過去問を解くのは、いつ頃から始めればいいですか?
大阪府立高校の過去問を解き始めるのは、夏期講習が終わった9〜10月がおすすめです。
9〜10月と早い時期に解いておくことで、入試問題の出題形式を把握し、現時点での苦手分野を知ることができます。ただし、学校の進度によっては未履習単元があり、解けない可能性もあります。
一般入学者選抜は3月に実施されるため、9月頃から過去問を解き始めれば、焦ることなく入試対策を進められるでしょう。演習問題や出題傾向のポイントを抑えるためにも、過去5年分は過去問を解くことをおすすめします。
【春期講習会 無料】
2026年度 新年度生募集!

まとめ
本記事では、大阪府立高校の入試問題であるA・B・Cの各出題形式や大阪府立高校の入試の特徴について解説しました。
大阪公立高校は学力検査だけではなく内申点も合否判定に影響するため、学校の定期テストでいい点数を取るのはもちろん、授業中の態度、出席状況などの日常的な評価も意識する必要があるでしょう。
また、文理学科などハイレベルの高校では、C問題を出題することが多く、教科書レベルではなく応用問題の対策が必須になります。
特に英語のC問題では問題文も含め、すべて英語で出題され、難易度がとても高いです。受験を有利に進めるためにも、英検やTOEFL iBTなど外部機関の資格を取得できるよう、中学1年生から計画しておきましょう。